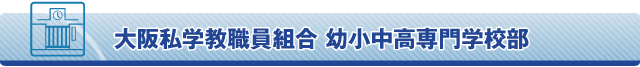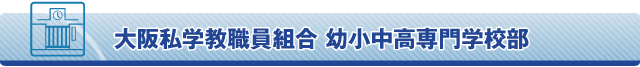���c�����E�����E���w��������
|
2009/2/16
| ���{�̐V���ȁu�������Z����U���v���
���w���ǂ��֓�����
| | �Q�O�O�T�^�O�T�^�Q�S
�s�������֘A�����t
�@
�@���{���{�́A���ېl���K��u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��v(�Љ�K��B�`�K��j���P�X�V�X�N�ɔ�y���܂������A���̂����A�����E��������̑Q�i�I���������߂���P�R���Q���i���j�i���j���͂��߁A�S�̏����ɂ��ė��ۂ������Ă��܂��B
�@�������疳���������𗯕ۂ��Ă��鍑�́A���P�T�P�J���i�Q�O�O�T�N�P���Q�T�����݁j�̂����A���{�A�}�_�J�X�J���A�������_�̂R�J���݂̂ł��B
�@�Љ�K��̒��́A���̋K���搂�ꂽ�����̎����̂��߂ɂƂ����[�u�Ȃǂɂ��āA���A�ɒ�����s�����Ƃ��`���Â����Ă��܂����A�Q�O�O�P�N�ɓ��{���{����o������Q��ɑ��āA���A�́u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���ψ���v�i�Љ�K��ψ���j�͒����E�R�����s�����̂��A�u�ŏI�����v�\���A���ۂ̓P����������邱�Ƃ��������߂錵�����������s���܂����B�܂����̒��ŁA�Q�O�O�U�N�U���R�O���܂łɑ�R����o���A�����ł��̊��������{���邽�߂ɂƂ����[�u�ɂ��ďڍׂɕ��邱�Ƃ�v������Ă��܂��B
�@
�@�ȉ��ɁA���̂��̂����Ă��܂��B
�@�C�j�u���E�l���錾�v
�@�n�j�u�s���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��̑I���c�菑�v
�@�j�j��y�̍ۂ̓��{�̏���
�@�z�j�u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���K��v�i���ېl���K��`�K��A�Љ�K��j��V��
�@�w�j�u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���K��v�i���ېl���K��`�K��A�Љ�K��j��W��
�@�g�j�u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���K��v�i���ېl���K��`�K��A�Љ�K��j��P�R��
�@�`�j�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���ψ����̎��⎖���ɑ�����{���{��
�@���j�Љ�K��ψ���́u�ŏI�����v�i2001�N8��30���̑��A�O���ȉ���j
�@ǁj�q�ǂ��̌������i�P�X�W�X�N�j��Q�W��
�@���j���@�i�P�X�S�V�N3�j��14���26��
�@���j�����{�@�i�P�X�S�V�N�j��P���R���U���P�O��
�@���j�����w�Z�@�i�P�X�S�X�N�j
�@�J�j�����w�Z�U�������@�i�P�X�V�T�N�j
�@���j�w�K���錾�i1985.3.�p���j
�C�j�u���E�l���錾�v
�@
�@�P�X�S�W�N�P�Q���P�O�����A����ɂ����č̑��B
�@�@�I�ȍS���͂͂Ȃ����l���y�ю��R�d���m�ۂ��邽�߂ɁA���ׂĂ̐l���Ƃ��ׂĂ̍��Ƃ��B�����ׂ����ʂ̊���߂����́B
�@�P�X�T�O�N�A���A����ɂ����āA���N12��10�����u�l���f�[�v�iHuman Rights Day�j�Ƃ��āA���E���ŋL�O�s�����s�����Ƃ����c����܂����B
�@
���j�u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���K��v�i���ېl���K��`�K��A�Љ�K��j
���j�u�s���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��v�i�a�K��j
�@
�@���ɁA�P�X�U�U�N�P�Q���P�U���̑��A�`�K��́A�P�X�V�U�N�P���R�����s�A�a�K��P�X�V�U�N�R���Q�R������
�@�@�I�ȍS���͂����B
�@���{�́A�P�X�V�X�N�U���Q�P���ꕔ�������Ĕ�y
�@
�n�j�u�s���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��̑I���c�菑�v
�@
�@B�K��̎��{�Ɋ֘A���āA���K��Ɍf���錠���̐N�Q�ɂ��Ē��̌l���s�����ʕ�����̋K��ɂ���Đ݂���ꂽ�l���ψ���R�c���鐧�x�ɂ��ċK�肵�����̂��̑����ꂽ�i���݂́A�u���I���c�菑�v�j�B
�@
�j�j��y�̍ۂ̓��{�̏���
�@
�@���{�́A���̋K��̔�y���̊���ɓ�����A�����̍ۂɍs���錾���m�F����|�̒ʍ������ۘA�������������ď��Ȃɂ��s�����B
�@
�@���Ȃ����Č[�ア�����܂��B�{�g�́A�{�����{�ɑ���A���{�����{�͌o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��y�юs���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK����y����ɓ����菐���̍ۂɍs�����̐錾���m�F���邱�Ƃ�ʍ�������h��L���܂��B
�P�@���{���́A�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��掵���i���j�̋K��̓K�p�ɓ�����A�@���̋K��ɂ����u���̋x���ɂ��Ă̕�V�v�ɍS������Ȃ������𗯕ۂ���B
�Q�@���{���́A�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK��攪���P�i���j�̋K��ɍS������Ȃ��@�����𗯕ۂ���B�������A���{�����{�ɂ�铯�K��̔�y�̎��ɓ��{���̖@�߂ɂ��O�L�̋K��Ɂ@�����������^�����Ă��镔��ɂ��ẮA���̌���łȂ��B
�R�@���{���́A�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK���\�O���Q�i���j�y�сi���j�̋K��̓K�@�p�ɓ�����A�����̋K��ɂ����u���ɁA��������̑Q�i�I�ȓ����ɂ��v�ɍS������Ȃ������𗯕ہ@����B
�S�@���{�����{�́A���Ђ̎��R�y�ђc�����̕ی�Ɋւ�����̔�y�ɍۂ����������ɂ����u�x�@�@�v�ɂ͓��{���̏��h���܂܂��Ɖ�����|�̗�����Ƃ����Ƃ�z�N���A�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����@�I�����Ɋւ��鍑�ۋK��攪���Q�y�юs���I�y�ѐ����I�����Ɋւ��鍑�ۋK����\����Q�ɂ��@���u�x�@�̍\�����v�ɂ͓��{���̏��h�E�����܂܂��Ɖ��߂�����̂ł��邱�Ƃ�錾����B
�@�{�g�́A�ȏ��\���i�߂�ɍۂ��A�����Ɋt���Ɍ����Čh�ӂ�\���܂��B
�@���S���\��N�Z����\���
���ۘA�����{���{��\�@�@�@
�����S����g�@���{�M�i�����j
�@
�z�j�u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���K��v�i���ېl���K��`�K��A�Љ�K��j��V��
�@
�掵��
�@���̋K��̒��́A���ׂĂ̎҂��������ǍD�ȘJ�����������錠����L���邱�Ƃ�F�߂�B���̘J�������́A���Ɏ��̂��̂��m�ۂ���J�������Ƃ���B
�@�i���j���ׂĂ̘J���҂ɍŏ����x���̂��̂�^�����V
�@�@�ii�j�����Ȏ����y�т����Ȃ鍷�ʂ��Ȃ����ꉿ�l�̘J���ɂ��Ă̓����V�B���ɁA���q�ɂ� �ẮA����̘J���ɂ��Ă̓����V�ƂƂ��ɒj�q������J�������ɗ��Ȃ��J������ ���ۏႳ��邱�ƁB
�@�@�iii�j�J���ҋy�т��̉Ƒ��̂��̋K��ɓK�����鑊���Ȑ���
�@�i���j���S�����N�I�ȍ�Ə���
�@�i���j��C�y�є\�͈ȊO�̂����Ȃ鎖�R���l������邱�ƂȂ��A���ׂĂ̎҂����̌ٗp�W�ɂ����Ă�@�@�荂���ߓ��Ȓn�ʂɏ��i����ϓ��ȋ@��
�@�i���j�x���A�]�ɁA�J�����Ԃ̍����I�Ȑ����y�ђ���I�ȗL���x�ɕ��тɌ��̋x���ɂ��Ă̕�V
�@
�w�j�u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���K��v�i���ېl���K��`�K��A�Љ�K��j��W��
�@
�攪��
�P�@���̋K��̒��́A���̌������m�ۂ��邱�Ƃ����B
�@�i���j���ׂĂ̎҂����̌o�ϓI�y�юЉ�I���v�i���y�ѕی삷�邽�߁A�J���g�����������y�с@�@���Y�J���g���̋K���ɂ̂ݏ]�����Ƃ������Ƃ��Ď���I������J���g���ɉ������錠���B���̌��@�@���̍s�g�ɂ��ẮA�@���Œ�߂鐧���ł��č��̈��S�Ⴕ���͌��̒����̂��ߖ��͑��̎ҁ@�@�̌����y�ю��R�̕ی�̂��ߖ���I�Љ�ɂ����ĕK�v�Ȃ��̈ȊO�̂����Ȃ鐧�����ۂ��邱�Ƃ��@�@�ł��Ȃ��B
�@�i���j�J���g���������̘A�����͑��A����ݗ����錠���y�т����̘A�����͑��A�������ۓI�ȘJ�@�@���g���c�̂����������͂���ɉ������錠��
�@�i���j�J���g�����A�@���Œ�߂鐧���ł��č��̈��S�Ⴕ���͌��̒����̂��ߖ��͑��̎҂̌����y�@�@�ю��R�̕ی�̂��ߖ���I�Љ�ɂ����ĕK�v�Ȃ��̈ȊO�̂����Ȃ鐧�����邱�ƂȂ��A���R�@�@�Ɋ������錠��
�@�i���j������Ƃ����錠���B�������A���̌����́A�e���̖@���ɏ]�čs�g����邱�Ƃ������Ƃ���B
�Q�@���̏��̋K��́A�R���Ⴕ���͌x�@�̍\�������͌������ɂ��P�̌����̍s�g�ɂ��č��@�I�ȁ@�������ۂ��邱�Ƃ�W������̂ł͂Ȃ��B
�R�@���̏��̂����Ȃ�K����A���Ђ̎��R�y�ђc�����̕ی�Ɋւ�����S�l�\���N�̍��ۘJ���@�@�ւ̏��̒����A�����ɋK�肷��ۏ��j�Q����悤�ȗ��@�[�u���u���邱�Ɩ��͓����Ɂ@�K�肷��ۏ��j�Q����悤�ȕ��@�ɂ��@����K�p���邱�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��B
�@
�g�j�u�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���K��v�i���ېl���K��`�K��A�Љ�K��j��P�R��
�@
��\�O��
�P�@���̋K��̒��́A����ɂ��Ă̂��ׂĂ̎҂̌�����F�߂�B���́A���炪�l�i�̊����@�y�ѐl�i�̑����ɂ��Ă̈ӎ��̏\���Ȕ��B���w�������тɐl���y�ъ�{�I���R�̑��d�������@���ׂ����Ƃɓ��ӂ���B�X�ɁA���́A���炪�A���ׂĂ̎҂ɑ��A���R�ȎЉ�Ɍ��ʓI�ɎQ�����@�邱�ƁA�������̊ԋy�ѐl��I�A�푰�I���͏@���I�W�c�̊Ԃ̗����A���e�y�їF�D�𑣐i���邱�Ɓ@���тɕ��a�̈ێ��̂��߂̍��ۘA���̊������������邱�Ƃ��\�ɂ��ׂ����Ƃɓ��ӂ���B
�Q�@���̋K��̒��́A�P�̌����̊��S�Ȏ�����B�����邽�߁A���̂��Ƃ�F�߂�B
�@�i���j��������́A�`���I�Ȃ��̂Ƃ��A���ׂĂ̎҂ɑ��Ė����̂��̂Ƃ��邱�ƁB
�@�i���j��X�̌`�Ԃ̒�������i�Z�p�I�y�ѐE�ƓI����������܂ށB�j�́A���ׂĂ̓K���ȕ��@�ɂ��A�@�@���ɁA��������̑Q�i�I�ȓ����ɂ��A��ʓI�ɗ��p�\�ł���A���A���ׂĂ̎҂ɑ��ċ@��@�@���^��������̂Ƃ��邱�ƁB
�@�i���j��������́A���ׂĂ̓K���ȕ��@�ɂ��A���ɁA��������̑Q�i�I�ȓ����ɂ��A�\�͂ɉ����A�@�@���ׂĂ̎҂ɑ��ċϓ��ɋ@��^��������̂Ƃ��邱�ƁB
�@�i���j��b����́A����������Ȃ����Җ��͂��̑S�ے����C�����Ȃ����҂̂��߁A�ł������@�@���コ�ꖔ�͋�������邱�ƁB
�@�i���j���ׂĂ̒i�K�ɂ킽��w�Z���x�̔��W��ϋɓI�ɒNj����A�K���ȏ��w�����x��ݗ����y�ы��@�@��E���̕����I������s�f�ɉ��P���邱�ƁB
�R�@���̋K��̒��́A����y�яꍇ�ɂ��@��ی�҂��A���̋@�ւɂ�Đݒu�����w�Z�ȊO�@�̊w�Z�ł��č��ɂ�Ē�߂�ꖔ�͏��F�����Œ���x�̋����̊�ɓK��������̂����@���̂��߂ɑI�����鎩�R���тɎ��Ȃ̐M�O�ɏ]�Ď����̏@���I�y�ѓ����I������m�ۂ��鎩�@�R��L���邱�Ƃd���邱�Ƃ����B
�S�@���̏��̂����Ȃ�K����A�l�y�ђc�̂�����@�ւ�ݒu���y�ъǗ����鎩�R��W������̂Ɖ����@�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A��ɁA�P�ɒ�߂錴�������炳��邱�Ƌy�ѓ��Y����@�ւɂ����čs�Ȃ���@���炪���ɂ�Ē�߂���Œ���x�̊�ɓK�����邱�Ƃ������Ƃ���B
�@
�`�j�o�ϓI�A�Љ�I�y�ѕ����I�����Ɋւ���ψ����̎��⎖���ɑ�����{���{��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�O���ȉ���j�i�Q�O�O�P�N�j
�@
�T�D�Љ�K���{����Ă����ʓI�g�g��
��Q�D�Љ�K��̑�V���i���j�A��P�R���Q�i���j�y�ё�P�R���Q�i���j�ւ̗��ۂ��ێ�����K�v���ɂ��Đ��@�����ĉ������B�����̗��ۂ�P�邽�߂ɓ��{���v�悵�Ă���^�C���X�P�W���[������ĉ����@���B
��
�Q�D��P�R���Q�i���j�y�сi���j�ւ̗���
�i1�j �䂪���ɂ����ẮA�`������I����̌����������y�э�������ɌW��o��ɂ��āA��i�w�@�҂Ƃ̕��S�̌����̌��n����A���Y�������w�����ɑ��ēK���ȕ��S�����߂�Ƃ������j���Ɓ@���Ă���B
�@�܂��A��������i��w�j�ɂ����Ď����w�Z�̐�߂銄���̑傫�����Ƃ�����A��������̖������̕��@�j���̂邱�Ƃ́A����ł���B
�@�Ȃ��A�����������y�э�������ɌW��@��ϓ��̎����ɂ��ẮA�o�ϓI�ȗ��R�ɂ��C�w���@��Ȏ҂ɑ��鏧�w�����x�A���Ɨ����Ƒ[�u���̏[����ʂ��Đ��i���Ă���B
�i2�j ���������āA�䂪���́A�Љ�K���P�R���Q�i���j�y�сi���j�̋K��̓K�p�ɂ�����A�����̋K��Ɂ@�����u���ɁA��������̑Q�i�I�ȓ����ɂ��v�ɍS������Ȃ������𗯕ۂ��Ă���B
�@
���j�Љ�K��ψ���́u�ŏI�����v�i2001�N8��30���̑��A�O���ȉ���j
�@
�b�D��Ȍ��O�������
�P�O�D�ψ���́A���̋K���V���id�j�A��W���Q���A��P�R���Q���ib�j�y�сic�j�ւ̗��ۂɊւ��A�ψ���@����������ɂ��A�����̌����̊��S�Ȏ����͂܂��ۏႳ��Ă��Ȃ����Ƃ�������Ă���@����A�����O�q�̏����ŕۏႳ�ꂽ���������Ȃ�̒��x�������Ă���Ƃ������R�Ɋ�Â��āA���@�ۂ�P��Ӑ}���Ȃ����Ƃɓ��Ɍ��O��\������B
�@�@�i�O���Ȓ��F��8 ���ɂ��ė��ۂ��Ă���̂́A��2 ���ł͂Ȃ���1 ���id�j�ł���B�j
�d�D�y�ъ���
�R�S�D�ψ���́A���ɑ��A�K���V���id�j�A��W���Q���A���тɑ�P�R���Q���ib�j�y�сic�j�ւ̗��ۂ́@�P����������邱�Ƃ�v������B
�U�Q�D�ψ���́A���ɑ��A�Љ�̑S�Ă̑w�ɍŏI�������L���z�z���A�����̎��{�̂��߂ɂƂ����@���ׂĂ̑[�u�ɂ��Ĉψ���ɕ��邱�Ƃ���������B�܂��A�ψ���́A���ɑ��A��R���@���쐬�����̑����i�K�ɂ����āANGO �y�ё��̎s���Љ�̍\�����Ƌ��c���邱�Ƃ���������B
�U�R�D�Ō�ɁA�ψ���́A���ɑ��A��R����Q�O�O�U�N�U���R�O���܂łɒ�o���A���̒̕��@�@�ɁA���̍ŏI�����Ɋ܂܂�Ă��銩�������{���邽�߂ɂƂ�����i�ɂ��ẮA�ڍׂȏ����܂߂�@���Ƃ�v������B
�@�@�i���P�F���́u���v�́A���{�������j
�@�@�i���Q�F�i���`���̔ԍ��́A�u�ŏI�����v�S���ʂ��̒i���ԍ��B�U�R���ŏI�i���j
�@
ǁj�q�ǂ��̌������i�P�X�W�X�N�j��Q�W��
�@
��Q�W�� �i����ւ̌����j
�P�@���́A�q�ǂ��̋���ւ̌�����F�߁A���A�Q�i�I�ɂ���ѕ����ȋ@��Ɋ�Â��Ă��̌����@��B�����邽�߂ɁA�Ƃ��Ɏ��̂��Ƃ�����B
�@���D����������`���I�Ȃ��̂Ƃ��A�����ׂĂ̎҂ɑ��Ė����Ƃ��邱�ƁB
�@���D��ʋ��炨��ѐE�Ƌ�����܂ގ�X�̌`�Ԃ̒�������̔��W�����サ�A���ׂĂ̎q�ǂ������p�@�@�\�ł��肩�A�N�Z�X�ł���悤�ɂ��A�Ȃ�тɁA��������̓�������ѕK�v�ȏꍇ�ɂ͍����I�@�@�����̒Ȃǂ̓K���ȑ[�u���Ƃ邱�ƁB
�@���D����������A���ׂĂ̓K���ȕ��@�ɂ��A�\�͂Ɋ�Â��Ă��ׂĂ̎҂��A�N�Z�X�ł�����̂Ƃ���@�@���ƁB
�@���D����エ��ѐE�Ə�̏��Ȃ�тɎw�����A���ׂĂ̎q�ǂ������p�\�ł��肩�A�N�Z�X�ł��@�@����̂Ƃ��邱�ƁB
�@���D�w�Z�ւ̒���I�ȏo�Ȃ���ђ��r�ފw���̌��������シ�邽�߂̑[�u���Ƃ邱�ƁB
�Q�@���́A�w�Z�������q�ǂ��̐l�Ԃ̑����ƈ�v������@�ŁA�����̏��ɏ]���čs���邱�Ɓ@���m�ۂ��邽�߂ɂ�����K���ȑ[�u���Ƃ�B
�R�@���́A�Ƃ��ɁA���E���̖��m����є�E���̍���ɍv�����邽�߂ɁA���Ȋw�I����ыZ�p�@�I�m���Ȃ�тɍŐV�̋�����@�ւ̃A�N�Z�X���������邽�߂ɁA����Ɋւ�����ɂ��č��ۋ��@�͂𑣐i�������シ��B���̓_�ɂ��ẮA���W�r�㍑�̃j�[�Y�ɓ��ʂ̍l����
�@
���j���@�i�P�X�S�V�N3�j��14���26��
�@
��14���i�@�̉��̕����j
�@���ׂč����́A�@�̉��ɕ����ł����āA�l��A�M���A���ʁA�Љ�I�g�����͖�n�ɂ��A�����I�A�o�ϓI���͎Љ�I�W�ɂ����āA���ʂ���Ȃ��B
��26���i������錠���j�@
�P�D���ׂč����́A�@���̒�߂�Ƃ���ɂ��A���̔\�͂ɉ����āA�ЂƂ���������錠����L����B
�Q�D���ׂĂ̍����́A�@���̒�߂�Ƃ���ɂ��A���̕ی삷��q���ɕ��ʋ����������`���@�@���B�`������́A������Ƃ���B
�@
���j�����{�@�i�P�X�S�V�N�j��P���R���U���P�O��
�@
��P���i����̖ړI�j
�@����́A�l�i�̊������߂����A���a�I�ȍ��Ƌy�юЉ�̌`���҂Ƃ��āA�^���Ɛ��`�������A�l�̉��l�сA�ΘJ�ƐӔC���d����I���_�ɏ[�����S�g�Ƃ��Ɍ��N�ȍ����̈琬�������čs�Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��R���i����̋@��ϓ��j
�@���ׂč����́A�ЂƂ����A���̔\�͂ɉ����鋳�����@���^�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł����āA�l��A�M���A���ʁA�Љ�I�g���A�o�ϓI�n�ʖ��͖�n�ɂ���āA����㍷�ʂ���Ȃ��B
��U���i�w�Z����j
�P�D�@���ɒ�߂�w�Z�́A���̐����������̂ł����āA�����͒n�������c�̂̊O�@���ɒ�߂�@�l�́@�݂��A�����ݒu���邱�Ƃ��ł���B
�Q�D�@���ɒ�߂�w�Z�̋����́A�S�̂̕�d�҂ł����āA���Ȃ̎g�������o���A���̐E�ӂ̐��s�ɓw�@�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�����̐g���́A���d����A���̑ҋ��̓K����������Ȃ���ȁ@��Ȃ��B
��P�O���i����s���j
�P�D����́A�s���Ȏx�z�ɕ����邱�ƂȂ��A�����S�̂ɑ����ڂɐӔC���čs�Ȃ���ׂ����̂ł��@��B
�Q�D����s���́A���̎��o�̂��ƂɁA����̖ړI�𐋍s����ɕK�v�ȏ������̐����m����ڕW�Ƃ��čs�@�Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
���j�����w�Z�@�i�P�X�S�X�N�j
�@
��P���i�ړI�j
�@���̖@���́A�����w�Z�̓����ɂ��݁A���̎��含���d�A�����������߂邱�Ƃɂ���Ď����w�Z�̌��S�Ȕ��W��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
��T�X���i�����j
�@�����͒n�������c�̂́A����̐U����K�v������ƔF�߂�ꍇ�ɂ́A�w�Z�ɑ��A�����w�Z����Ɋւ��K�v�ȏ��������邱�Ƃ��ł���B
�@
�J�j�����w�Z�U�������@�i�P�X�V�T�N�j
�@
��P���i�ړI�j
�@���̖@���͊w�Z����ɂ����鎄���w�Z�̉ʂ����d�v�Ȗ����ɂ��݁A���y�ђn�������c�̂��s�Ȃ������w�Z�ɑ��鏕���̑[�u�ɂ��ċK�肷�邱�Ƃɂ��A�����w�Z�̋�������̈ێ��y�ь�����тɎ����w�Z�ɍ݊w���鎙���A���k�A�w�����͗c���ɌW��C�w��̌o�ϓI���S�̌y����}��ƂƂ��Ɏ����w�Z�̌o�c�̌��S�������߁A�����Ď����w�Z�̌��S�Ȕ��B�Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
��R���i�w�Z�@�l�̐Ӗ��j
�@�w�Z�@�l�́A���̖@���̖ړI�ɂ��݁A����I�ɂ��̍�����Ղ̋�����}��A���̐ݒu����w�Z�ɍ݊w���鎙���A���k�A�w�����͗c���ɌW��C�w��̌o�ϓI���S�̓K������}��ƂƂ��ɁA���Y�w�Z�̋��琅���̌���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��S���i������w���̌o��I�o��ɂ��Ă̕⏕�j
�@���́A��w���͍������w�Z��ݒu����w�Z�@�l�ɑ��C���Y�w�Z�ɂ����鋳�疔�͌����ɌW��o��I�o��ɂ��āA���̂Q���̂P�ȓ���⏕���邱�Ƃ��ł���B
��X���i�w�Z�@�l�ɑ���s���{���̕⏕�ɑ��鍑�̕⏕�j
�@�s���{�������̋����ɂ��鏬�w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�A�ӊw�Z�A�W�w�Z�A�{��w�Z���͗c�t����ݒu����w�Z�@�l�ɑ��A���Y�w�Z�ɂ����鋳��ɌW��o��I�o��ɂ��ĕ⏕����ꍇ�ɂ́A���́A�s���{���ɑ��A���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���̈ꕔ��⏕���邱�Ƃ��ł���B
�@
���j�w�K���錾�i1985.3.�p���j
�@
�i��S�l�X�R���ې��l����錾�j
�@�w�K���̏��F�́A���܂�A����܂ňȏ�ɁA�l�ނɂƂ��āA�d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B
�@
�@�w�K���Ƃ́A
�@�ǂݏ����̌����ł���A
�@���₵�A�n�����錠���ł���A
�@�z�����A����o�������ł���A
�@�������g�̐��E��ǂ݂Ƃ�A���j����錠���ł���A
�@����̋@��ɐڂ��錠���ł���A
�@�l�I�E�W�c�I�Z�\���̂������ł���B
�@
�@���l����p����c�́A���̌����̏d�v�����Ċm�F����B
�@�w�K���́A�����̂�����̂��߂ɗ\�ꂽ�����I���������i�ł͂Ȃ��B����͊�b�I�~�����݂����ꂽ���Ƃɗ^������A���i�K�̂��̂ł͂Ȃ��B
�@�w�K���́A�l�������̂т�ɕs���ȓ���ł���B
�@���E�̂ЂƂтƂ́A�����H�Ɛ��Y�ƁA���̑��̐l�ԓI�~���݂̂�����邱�Ƃ��̂��ނȂ�A�w�K���������˂Ȃ�Ȃ��B
�@�����ƒj�����A���悢���N�����邽�߂ɂ́A�ނ�́A�w�K���������˂Ȃ�Ȃ��B
�@��������ꂪ�푈�������悤����Ȃ�A���a�ɐ����邱�Ƃ��w�сA���������ɗ���������˂Ȃ�Ȃ��B�u�w�K�v�̓L�[���[�h�ł���B
�@�w�K���Ȃ��ɁA���l���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�w�K���Ȃ��ɁA�_�ƂƍH�Ƃ̖��i���A�n��ی����A�����Ď��ہA�w�K�����̕ω����Ȃ��ł��낤�B
�@���̌����Ȃ��ɂ́A�s�s��_���ł͂��炭�l�����̐��������̉��P���Ȃ��ł��낤�B
�@���Ȃ킿�A�w�K���́A���݂̐l�ނɂƂ��Đ[���Ȗ�����������̂ɁA�����Ƃ��v���ł�����̂̂ЂƂȂ̂ł���B
�@�������A�w�K���́A�P�Ȃ�o�ϔ��W�̎�i�ł͂Ȃ��B����͊�{�I�����̂ЂƂƂ��āA�F�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�w�K�����͂����鋳�犈���̒��S�Ɉʒu�t�����A�ЂƂтƂ��Ȃ����܂܂ɓ��������q�̂���A�����̗��j�����o����̂ɂ����Ă������̂ł���B
�@����͂ЂƂ̊�{�I�l���̂ł���A���̍��@���͖��l�ɋ��ʂ��Ă���B�w�K���͐l�ނ̈ꕔ�̂��̂Ɍ��肳��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����́A�j����H�ƍ���L�Y�K����w�Z���������K���Ȏ�҂����̔r���I�����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�㗪�j�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�@�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| ���{�̐V���ȁu�������Z����U���v���
���w���ǂ��֓�����
�@�\�\�u�w21���I�̎��������w�Z����U���̂�������k��x�v�ᔻ
2000�N10���@
�厄���������Z�����s�ψ���
��A�w�x�̓��قȐ��i
�P�D���{�E���E�̐V���R��`�I�u������v�v�Ɏ��������w�Z���]��������錾
�@�u�c�c���̓����̑R���Ƃ��Đ��̑�オ����̓`���╶���������͂����邱�Ƃ��A�킪���̃o�����X���锭�W�̂��߂ɕK�v�ł���A����ɂӂ��킵������̂�������l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�{���k��́A���������ϓ_�ɗ����āA����̑��{�̎��������w�Z�̂�����ɂ��Ē��邱�Ƃ��ۑ�Ƃ��ė^����ꂽ�c�c�v�@�@
�@�u21���I�̎��������w�Z����U���̂�������k��v�i�ȉ��u���k��v�A��1�j�́A����9��19���A�u���k��v�̐R�c�̂܂Ƃ߂��w�u21���I�̎��������w�Z����U���̂�������k��v�x�i�ȉ��w�x�j�Ƃ��đ��c�m���ɒ�o���܂������A�u���k��v�̍������Ƃ߂��V�x���玁�i���ɐ쏗�q��w�����j�́A���́u�������v�ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�@�w�x�͂��̉ۑ���ǂ̂悤�ɋ�̉��������B���̓��e�̓����́A�����悻���̒ʂ�ł��B
�@���オ��̎��w����ɂ��������Z�̓��p���ƌ��������팸�̑��i
�A���w�����u�č\�z�v�Ə̂���I�ʓI���w�����i�@�֕⏕�j���x�ւ̈ڍs
�B�u�����i�������v�̖��ɂ��u�@��ϓ������v�̋��Ɓu��v�ҕ��S�v�̓O��A�����̋��������̐����B�������Z���Ɨ��l�グ�ƕ��ꕉ�S���A�������Z�����Ɨ��⏕�́u�~�n���v�̋���
�C�������Z����̂��������́u���l���v���i�B���ʉȁu�Ώd�v�����ߐ��w�Ȃ�u�����w�ȁv���B���̂��߂́u���w�̓`���v�u���w�̐��_�̌������v�A����ł́u�@������v�ɂ��u�S�̋���v����B�I�ʂ̘_���Ƃ��Ắu���F�E���́v�u�n�����v�u���l���v�ȂǍ��E�E�����}�u������v�v�̎��w�ւ̎������݁E�����t��
�D���w�o�c�̂��������́u�������v�A�l���l�ۍ���̓����ɂ�郊�X�g�����i�Ƌ��E���̔\�͎�`�I�Ǘ��̐V���ȋ���
�E�u�s�ꌴ���E���������v�̓O��ɂ��������́A���������Z�̓��p���A�X�N���b�v�E�A���h�E�r���h�H���̐��i�A����������ɏ]��������u�\���o�����킹�̊w�Z�Ԃ��v
�@���́w�x�̗���́A����߂ē��قł��B
�@��P�ɁA�V�u�����v��v��u���Y�ƍĐ��v���O�����i�āj�v�ȂǂŁA���c�m���͏��q���Ƒ��{�����̔j�]�������ɁA�����E�̈ӌ���S�ʓI�ɓ��܂��A�u���̊��͂̉v���ő�̐����ڕW�Ƃ��A���̍s���ڕW�Ɏ������Z���炻�̂��̂��]�������邱�Ƃ������炳�܂ɐ錾���Ă͂���܂���B���Ȃ݂ɁA�V�u�����v��v�ł́u�c�c���q���̐i�s�ɂ�鎙�����k���̌����ɂ��A�����w�Z���Ƃ�܂����͔N�X�������Ȃ��Ă��Ă���A�e�w�Z�͂���w����̑n�ӍH�v�Ǝ����w�͂ɂ��A���琅���̈ێ�������͂���K�v������܂��v�Ƃ��A�u���Y�ƍĐ��v���O�����i�āj�v�ł́u�c�c�{�{�ł́A������͂���ޏA�Ƒ̌�����y�тh�s�����p��������̂��߂̎{�݁E�ݔ��̐������A�����w�Z�ɂ�������F�E���͂��鋳��̎��g�݂����i�����悤�x�����Ă����v�Ɩ������Ă���̂ł��B���c�m���̂��̂悤�ȗ��ꂪ�A�u�s���Ȏx�z�v���ւ��������{�@���̂��̂ɒ�G���邱�Ƃ͋ɂ߂Ė����ł����A�w�x�u�������v�́A���̉����c�ł��邱�Ƃ����玦���Ă���_�ł��B
�@��Q�ɁA���̂��ƂƊւ��܂����A�w�x�́A�Љ�a�������鋳��r�p�̍L����⎄�������w�Z�̌���̋ꂵ�݂ɂ��āA��ڂ��ɂ��܂���B
�@�u17�̖\���v�A�o�Z���ہE���r�ފw�ȂǁA�����E���k�̐l�ԓI�����̘c�݁A�u�w�т���̓����v�i�����w���j�E�u���ƕs�����v���A�����Ȋw�K����ȂǐV���ȋ���r�p�̍L����̍����́A�����I�ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@���w�̌���ł́A���{�̕n���Ȏ��w���������w�i�ɁA��C���@�̗̍p��T���ƕs��[�Ȃnjo�c�҂̑��z�l����}���H���̂��ƂŁA���Y�ƘJ���҂͂������A�������E���ɔ䂵�Ă��ˏo�����ݐE���S���ɏے������[���Ȍ��N�j��Ɍ������Ȃ���A����ꓬ���鋳�E���A�Ƒ��������͂������A�u���e�̓��X�g���A�q�ǂ��̓t���[�^�[�v�ƌ�����ٗp�j��ɂ��炳��镃��A���k�̏Ȃǂɂ��āA�w�x�͂܂������������Ă�����̂ł��B�s�o�Z�⒆�r�ފw�����A�w�x�ɂ�����A������ł͂Ȃ��A�u�v��i�w���v�����グ�́u��Q�v�v�f�Ƃ��ĐG����Ă���ɂ����܂���B���̂悤�ȋ���_�c���܂����������A��������w�x�̗���̓��ق��́A�u������v�v���O�����i�āj�v�Ɣ�r���Ă������ۗ����̂ł��i��2�j�B
�@�����đ�R�ɁA�u�������Z����U���v�ƌ����Ȃ���A�������Z����̂�����ɂ܂Ō��y������Ȃ��������Ƃł��B���̂��Ƃ́A�����̃T�o�C�o�������̑g�D���ƁA���̑��i�̒S����Ƃ��Ă̎������Z����u�U���v����m������A�Ƃ������c�{���E�w�x�̖{���I�Ȃ˂炢���琶�܂�Ă��܂��B
�Q�D�S�����߂Ă̐V���R��`�ɂ�郉�W�J���Ȏ��w�u�U���v��̐錾
�@�@�V���R��`�I����u���v�v�́A�悭�m���Ă���悤�Ɂu�s�ꌴ���E���������v������̌����Ƃ��A����ւ̌���x�o�̍팸�Ƌ���E�w�Z�̏��i���A���E�́u21���I�헪�v��S���V���ȘJ���͂̑n�o���͂��鋳��̕ώ���ʂ��Č�����̏k���E��̂��w����c�t���Ɏ���܂ŁA�܂��Ɂu��ォ��쉺�v�܂Ŋт����s���悤�Ƃ�����̂��B����͒����R�H���ƍ��E�E�����}�u������v�v���x����d�v�Ȑ����I���ƂȂ��Ă��܂��i��3�j�B
�@�@���̂悤�ȁu���v�v�H���̂��ƂŁA���w�����ɂ��ĐV���R��`�҂��A�������Č��s�̌o���⏕���u������I�v�u�쑗�D�c��������������v�ȂǂƂ��Ĕr�����A�u�����I�E�d�_�z���v�����Ə��w�����x�ւ̓]�����咣���Ă��邱�Ƃ͏d��ł��i��4�j�B
�@�@�w�x�́A�u���w�����̍č\�z�v�Ə̂��A�o�����́u�d�_�z���v�A���Ɨ��Ə��w���̃����N�ȂǁA����x�o�̍팸���͂���A�������Z�ɂ́A�����A�����Ƃ̂͂Ă��Ȃ������Ɓu���{�I�Ȍo�c���v�v��v�����A����E�{���ɂ́A��w�̊w��S�������A�u�I���̎��R�v�Ƃ������́u�I���̕s���R�v�̍s�g�����߂Ă���̂ł��B�T�^�I�ȐV���R��`�ɂ�鎄�w����̕\���ł��B
�@�@�w�x���g���������Ă���悤�ɁA���i�K�ł͂������A�s���{�����׃��ɂ����Ă����̂悤�ȐV���R��`�ɂ�鎄�w�u�U���v�����ł��o�����̂́A���{�����߂Ăł��i��5�j�B
�@�@�����ɁA�����Ƃ��Ȃ��_�́A���{�͂��łɍ�N�u������v�v���O�����i�āj�v�\���A�������Z�̏k���E��̂ȂǐV���R��`�I����u���v�v����̓I�ɐ��i���Ă��܂����A�w�x���A���w�����̈ꗃ�ɑg�ݍ��݁A�ނ��낻�̐��i�́A�敺�Ƃ��Ċ��p���͂��낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃł��B
�@�@�w�x�̔������͊e�������A�ɑ傫�ȏՌ���^���Ă��܂��B�����ɁA���w�̒S�����ǂɂ��g����L���Ă��܂��B�����s�w�����́A�u����͂Ђǂ��B����s���̈�E���B�����I���e���v�Ƃ��Ă���̂ł��B
�@
�R�D�����}�{���̈�т������w����̋A��
�@�@�w�x�̂��̂悤�ȓ��قȐ��i�́A�ˑR���܂ꂽ���̂ł͂���܂���B�����}�����Ɏx�z����Â��Ă������{�̈�т������w��������̋A���Ƃ��ĂƂ炦��K�v������܂��i��6�j�B
�@�Ƃ�킯�A�����̑��{���w����̓y���z���A�w�x�ւ̏o�������������̂��A�ݒm���ł����B���̎��w����́A1983�N8���A���{�������Z����U�����k��i�����E�ʓc�`���A���{�Ȋw�Z�p�Z���^�[�햱�����j�́w�����̎������Z����ւ̒\�\���������������A21���I�ւ̔��W���߂����x�i�ȉ��w�����ւ̒x�j�ɏW��I�Ɏ�����Ă��܂��B
�@���́w�����ւ̒x�́A���k�}�����ɂ����钆�]���Ւ��E�s�v�H���̑S�����̋�̓I�Ȏ��w�����łƂ������i�������̂ł����B�����́w�x�́A�S�����߂Ă̐V���R��`�ɂ�鎄�w�����ŁA�ƌ����܂������A�u�}�����v�u�}�����v�̈Ⴂ��������A���ʂ����s���p���ɗ����Ă���A�S���ɂ͗�̂Ȃ����قȎp���ł��B�Ȃ���ォ�琶�܂��̂��B���̍ő�̗��R�́A���{�����A��т��Ď����}�����Ɏx�z����A�u�܂�Ŏ����}���t�̑��o�����v�Ə̂���Ă����悤�ɁA���������ɑS�ʓI�ɖӏ]����s���p�����Ƃ��Ă������Ƃɂ���܂��B���̂��Ƃ́A�u���w�U���c�����k��v�Ɍ�����悤�ɁA�S���ǂ������������{���Y�}��r�������u�I�[���^�}�̐��v�ɂ��c��x�z�����o�������ƂƖ��ڂɊւ���Ă��܂��B
�@�w�����ւ̒x�ȍ~�A�e�������Z�o�c�҂́A�}�����̜����ɋ����A�u�������鐶�k��20���v�̎���ƁA���i�E���ۉ����u���l���E���F���v�́u���͂��鎄�����Z����Â���v�֑S�ʓW�J����Ƃ���ƂȂ�܂����i��7�j�B
�R�D�u�O�l�l�r�v�̍���
�@�w�x�̈ψ��A���ʈψ��ɂ́A�������Z���E���̑�\����l������
����i��8�j�B�w�����ւ̒x���ʈψ��ɂ́A�厄����㖾�A�u��㎄�w
�����������߂��v�ۓc�F���A�勳�g�����N�p�̊e�����A21���̓��ʈ�
���̒��ɓ����Ă��܂����i�e���͂��ꂼ��̗��ꂩ��{���̋���v����
�����ĕ������܂������A�����̎咣�͂قƂ�Ǎ������ɂ���܂������j�B����́u���k��v�ł́A�����厄����\�ɂ����ʈψ��̗v�������w�ۂ��炠��܂������A�u���k��̐R�c�̗���ɂ�����Ȃ��v�Ƃ������R�ŁA�r�����ꂽ�̂ł��B���̂��ƂƁA���ɐG�ꂽ�w�x�̓��قȗ���Ƃ͂������[���ւ���Ă��܂��B
�@�u���k��v�ψ��̍\���́A�ꌩ���Ă����̕Ό��Ԃ肪�N���ł��B�厄���͂������A���J�A��u��㎄�w�����������߂��v���r������A���̈���ŁA�����E�A�u�A���v�A�V���R��`�̃I�s�j�I���E���[�_�[�A�����āA���w�W�҂���͑�㎄�����w�Z�����w�Z�A����O�E����A�ی�҉�A�����\�����O��A�˂Ă��܂��B
�@��Ɍ���悤�ɁA���J�E��c�����͂ނ���w�x�H����ϋɐ��i��
��������q�ϓI�ɒS�����ƂƂȂ������Ƃ܂���ƁA�w�x�́A����
���E����r�����A�s���Ɓu�L���ҁv�A�����Ď��w�o�c�ґ�\�́u�O�l�l�r�v
�ɂ�鍇��A�ƌ���ׂ��ł��傤�B
��A�w�x�͎������Z���ǂ��֓�����
�@�w�x�́A���q���Ƒ��{�����́u�����v���A�V���R��`�I����u���v�v�̍ő�̃������g�Ƃ��Ă��܂��B�u������C�O�悭�����ł��鎞��͏I������v�Ƃ��A���������E���w�����̍팸�R�����A�������Z�ɂ́A�����⑼�̎����ɕ����Ȃ��u���͂��鋳��Â���v�Ɓu���{�I�Ȍo�c���v�v�������v������̂ł��B�܂��A�u�I���̎��R�v��搂�����ɁA�����E�����̊e�w�Z�ԂɁA�ʂĂ��Ȃ����k�l��������g�D���悤�Ƃ��Ă��܂��B����ɁA�u�Y�ƊE�Ƃ̘A�g�v���A���E�̘J���͐���̘g�g�݂Ɏ������Z���Ƃ肱�ނ˂炢�܂ŁA�B�����Ƃ��Ă��܂���B
�@���̂悤�ȁw�x�H�����A�u������[�����Ȃ����Z�́A���̑�����Ղ����킴��Ȃ��v�ƒf������悤�ɁA�{���̑I�����Ȃ��������Z�̓��p���A�������Z�́u���R�����v�����̋A���_�Ƃ��邱�Ƃ́A�N�̖ڂɂ����炩�ł��B�ꈬ��́u�����g�v�ƈ��|�I�����́u�����g�v�����o���Ɠ����ɁA�����炻�̂��̂�ώ������A�������Z�̎��含�ւ̉���A�������̔��D���Đi�s���邱�ƂƂȂ�܂��B
�@�u�Y���w�v�����ɂ��������́E�k���H���̐敺�Ɏ������Z����������悤�Ƃ��Ă���̂ł��B������Ёu�n���v����̏o���Ƃ����A�O�㖢���̌ٗp����������ŕ������Ă��鏉�Ŗ��́A�܂��ɓT�^�Ƃ�����ł��傤�i��9�j�B
�@���̂悤�ȐV���R��`�I����u���v�v�𐄐i�����ŁA���@�E�����{�@�����s�@�̌n�́A�ő�̏�Q�ƂȂ�A�w�x�́A���́u�K���ɘa�v���ǂ̂悤�Ȍ`�ŋ�̉����A���̕ǂ�˔j���悤�Ƃ��Ă���̂��A���Ɍ��Ă݂邱�ƂƂ��܂��B
�P�D����s���̖@�I�Ӗ��̔ے�ƕώ�
(1)�@�������̐����ƑI���̎��R�̕ۏ�
�@�w�x�́A�u�s���͂�薣�͂��鎄�����Z�̐U�����W���x�����邽�߂̏��������ɓw�߂�K�v������v�Ƃ��A���̊�{���������̂Q�_�Ƃ��Ă��܂��B�u�������Z�̎���I�E�����I�ȉ��v�𑣂��A�����������܂߂��e�w�Z���݂��ɋ��������Ȃ���A���F�Ɩ��͂��ӂ����ǂ�������ł�����𐮂��邱�Ɓv�u���������̕ʂɊւ�炸�A�{���������A�S�A��]��\�́A�K���ɉ����č��Z�������̓I�����R�ɑI���ł���d�g�݂�x�𐮂��邱�Ɓv�B�܂�A���������̋����������邱�ƁA�I���̎��R��ۏႷ��d�g�݂Ɛ��x�𐮂��邱�Ƃ�����s���̖ړI�Ƃ���̂ł��B
�@����s���̖@�I�Ӗ��́A�����{�@��10���ɖ��m�ɋK�肳��Ă��܂��B�����́A�u����́A�s���Ȏx�z�ɕ����邱�ƂȂ�������S�̂ɑ����ڂɐӔC���čs�Ȃ���ׂ��ł���B
2�D����s���́A���̎��o�̂��ƂɁA����̖ړI�𐋍s����ɕK�v�ȏ������̐����m����ڕW�Ƃ��čs�Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɩ����Ă���̂ł��B�����ł����u����̖ړI�v�Ƃ́A���@�E�����{�@��A�w�Z����@�ŋK�肳�ꂽ����ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B
�@�w�x�́A���̂悤�ȋ����{�@�̖����鋳��s���̐Ӗ����܂����������A�Ȃ����͔ے肷��ԓx�𖾂炩�ɂ��Ă���̂ł��B
(2)�@���Z����́u���ڒv�Ɓu�w���ҁv�̎��_
�@�w�x�́A�������Z�����p���A����s���̔C���E������ώ������悤�Ƃ��Ă��܂��B���̂��Ƃ́u�����I�ȋ���s���̐��i�v�̍��ɂ����Ɏ�����Ă��܂��B
�@�u���k��l������̌���S�z�͎������Z���������Z�̖z�ƂȂ��Ă���B�����������Ƃ���A�������S���c�_����ۂɂ́A���������Z�ɓ������Ă��鋳�����g�[�^���łƂ炦�A���Z����ڒ��鎋
�_�����ł͂Ȃ��A�ŋ����g���ċ���T�[�r�X�����ǂ��w������Ƃ������_�����킹�����Ƃ��Ƃ��K�v�ł���v�Ǝ咣���܂��B
�@�v����ɁA�w�x�́A�������������Z�����オ��̎��w�̊��p���s���ɋ��߂Ă���̂ł��i��10�j�B���̂��Ƃ́A�u�������Z�ɂ�葽���̐��k��C����v�Ƃ����w�x�咣�ɂȂ����Ă����܂��B
�@������������Ƃ�������s���̖@�I�Ӗ����u���͂��鎄�����Z�̐U�����W���x��������������v�ɕώ������A�u����̋@��ϓ��v���A�u�w���҂̎��_�v�̋����ɂ��A�ے肷�邱�̂悤�ȁw�x�̎p���́A�܂��Ɍ��@�E�����{�@�ɑ���w�x���u�K���ɘa�v�̎�@�ƌ���˂Ȃ�܂���B
�Q�D�w�x�́A�ǂ̂悤�ȋ�̍���s���ɋ��߂Ă��邩�B
�u���͂��鎄�����Z�̐U�����W���x�����邽�߂̏��������v���s���ɋ��߂�w�x�́A�O�_�ɂ킽���āA���̋�̉����w�������Ă��܂��B
(1)�@�S�������Z�v��i�w���̈����グ�A����
�@�w�x�́A�u���k�����ɂ��A�{�ݖʂȂǂō��Z�ɐ��k����]�͂������Ă���v���ƁA�S�������Z�i�w��]���u��94���v�ŁA92.3���Ƃ���v��i�w���������Ă��邱�Ƃ�F�߂Ȃ���A�������A�v��i�w�������グ���咣���܂���B���̗��R�ɁA���w�Z�ɂ�����s�o�Z�A���Z�ł̒��r�ފw�̑����������Ă��܂��B���ꂪ�ǂ����Čv��i�w���������グ�邱�Ƃ��S�O������v���ƂȂ�̂ł��傤�B�������ɁA���w�ɂ�����s�o�Z���A�u�i�w��]���v�����������A���Z�̒��r�ފw�̑������A���������v��i�w���������グ�Ă��A�ǂ����r���ł�߂Ă��܂̂�����A�Ƃ����ӂ��ɍl�������Ƃ�����A����́A����{���̍��Z�i�w�v���݂ɂ��邱�ƂŁA���̊w�K���E���猠��N�Q������̂ł���A����e�F���邱�Ƃ͂ł��܂���B�u���̕�W����ł́A����������Ȃ��v�Ɣᔻ���錻�ꋳ�E���ɑ��A�u1�N����2�N�i������i�K�łQ�N���X�����炢�̒��r�ފw���o��v�ƁA�����Ԃ����������Z�o�c�҂����܂����A�ǂ����Ⴄ�̂ł��傤���B��10��R�c��ŁA�u�A���v�����ǒ����A�u���r�ފw�A�s�o�Z�́A�v��i�w�������グ�Ƃ͕ʌ̖��v�Ƃ��A�v��i�w���̈����グ���咣���܂������A���������R�̂��Ƃł��B����ɑ��A��Ɍ���悤�ɁA��c���́A�v��i�w���̈����グ�Ɋ拭�ɔ������̂ł��B
�@(2)�@�����̎���䗦�̒e�͉�
�@�u���������E�s�ꌴ���v������Ƃ���V���R��`�u���v�v�ɂƂ��āA�u�������e�䗦�v�͋K���ɘa�̏d�v�ȃ^�[�Q�b�g�ł��B
���s�̌������e�䗦�́A���������́u�K�x�̋����W�v�A�u�{���̎��R�Ȑi�H�I���v�̏�Ŗ�肪����A�Ɓw�x�͎w�E���܂��B�����āA�u�\�Ȍ�������Ԃ̕ی�ҕ��S�i���̐����Ƃ��������������s�Ȃ�����ŁA�e�͓I�Ȏ�����\�Ƃ�����@�ւ̕ύX����������K�v������v�Ǝ咣����̂ł��B
�@�v����ɁA�����̊w���i�K�I�Ɉ����グ�A�����̕ی�ҕ��S�i�����u�����v���A���̒��x�ɉ����āu�����V�F�A�[�v���u�e�͓I�v�Ɍ������A�Ƃ���̂ł��B
�@�������A�w�x�́A���X�Ԋi���ɂ��Ă͂܂������َE���Ă��܂��B�痢���ۍ��Z��100������w���A�����w�����Z��41���~�܂ŁA�ɒ[�Ȋw��i�������݂��܂��B��������ɂ��Ă��A�Ⴆ�P�w��������̕��ϐ��k��������ƁA���ˈ����Z��51.5�l���猚�����Z��16.5�l�̌��u������܂��i��������w��������݂����̎��w�x�A����12�N3���A���{�������w�Z�����w�Z�A����j�B
�@���̂悤�Ȋi���́A93�������Z�ɂ����Ă��u�K�x�̋����W�v��ۂ��ƁA�u�{���̎��R�Ȑi�H�I���v��ۏႷ�邱�Ƃ��d�v�ƔF������Ȃ�A���R�A����ƂȂ�͂��ł��B�������A�w�x�͂܂������������Ă������Ă��܂��B���̂��Ƃ́A�u���������v�u�������v�̐������u���X�ԁv�ɂ����Ă͂����߂���肪�܂������Ȃ����ƁA���Ȃ킿�������Z�ɂ��Ă͖��h���̂܂܃T�o�C�o���̐��E�ɓ����o���A�u�����c��v�͂����ς�e�������Z�́u�o�c�w�́v�ɑ҂��Ƃ̑ԓx�\���ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�l�グ�ł���w���Ƃł��Ȃ��w���A�ꍇ�ɂ��Βl�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��w���̓�ɕ����������݁A���X�Ԃɂ�����w��i��������j�i���͈�w�g�傷�邱�ƂƂȂ�܂��B
�@�������A���Ɂw�x����93�������Z�́u���������v�u�������v�𐮂��悤�Ƃ��Ă��A���̕����͈����w��������グ�A�u���X�Ԃ̕ی�ҕ��S�i�������v�Ƃ������ƂɂȂ炴��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��B
�@������ɂ��Ă��A��Ɍ���悤�ɁA�������Z�͂������A�������Z�w��ɂ��Ă����ꕉ�S�͌��E�ɒB���Ă��邱�Ƃ���A���̂悤�Ȉ�w�̕��ꕉ�S��������u�����i�������v�_�́A�u�I���̎��R�v�́u���������v�ƂȂ�ǂ��납�A�u�I���̕s���R�v����w�g�債�A�u�e�͉��v�ɑ���V���ȕ{���I�������ĂыN�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����I����ɗ��������X�Ԋi�������́A�厄�����ꓬ���ƘJ���ҁE����E�{���̋��������ɑ҂ȊO����܂���B
(3)�u����̋@��ϓ��v�̂���ւ��Ɓu�I���̕s���R�v
�@�u�����K�w�Ɋւ��Ȃ�����̋@��ϓ���ۏႵ�A�{���̎��R�ȍ��Z�I�����\�ƂȂ���������邽�߂̏d�v�ȉۑ�́A�����Ԃ̕ی�ҕ��S�i���̖��ł���v�B
�@�����ɂ͏d��ȓ�̖�肪����ł��܂��B
�@��P�́A�u����̋@��ϓ��v�́u�ۏ�v���A�u�����Ԃ̕ی�ҕ��S�i���v�Ƃ��������́u���������v�́u�����v�ɂ���ւ��Ă��邱�Ƃł��B���̌������Z���́u���Ɨ����Ɓv���x�K�p�҂́A47�s���{�����A�Q���������ł��B��㎄�����Z���̊w��ؔ[���A�o�ϓI���R�ɂ�钆�r�ފw�����ۗ������ł��B�����̎��Ԃ́A�������Z�w��̍����͌����܂ł��Ȃ��A�������Z���܂߁A�w��̂��̂��A�u�{���̌o�Ϗ�Ԃ̌������v����ς��������������ɂ��邱�Ƃ������Ă��܂��B�u�����K�w�Ɋւ���
������̋@��ϓ���ۏ�v���邽�߂ɂ͊w��S���̂��̂��Ȃ����Ȃ���Ȃ�܂���B���Ȃ��Ƃ����{�I�ȕ��S�y�����͂��邱�Ƃ��u�d�v�ȉۑ�v�ł��B�@�@
�@��Q�́A���̂��ƂƊւ���āA�w�x�̎咣����u�ی�ҕ��S�i�������v�_�́A�u�{���̎��R�ȍ��Z�I�����\�ƂȂ�������v���邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��_�ł��B
�@����́A�w�x���A�w��̕��ꕉ�S�̌y���Ƃ������_���܂������������킹�Ă��Ȃ�����ł��B���������X�Ԃ̊w��i���̐����ɂ��Ă͌�������Ă��܂��B�����Ȃ�A�����E�����̊w��̓����͒N�ł��\���\�ƂȂ�ł��傤�B�܂�A�������Z�w��͌��I�ɏ㏸�A�������Z�w��ɂ��Ă��l�グ�͔������������ƂƂȂ�܂��B�u��������ԁv�ɂ�����Ă��鈳�|�I�����̕{���ɂƂ��āA�w��S�̈�w�̊g��́A���̂܂܁u�I���̕s���R�v�̊g����Ӗ����܂��B�����̂��ƂŁA�w�x�̌����u�I���̎��R�v���s�g�ł���̂́A����ꂽ�K�w�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�����{�@��R���i����̋@��ϓ��j�́A���ʐ����֎~���鎖���Ƃ��āA���@��14���i�@�̉��̕����j�̖�����u�֎~�����v�Ɂu�o�ϓI�n�ʁv��t�����Ă��܂��B���̂��Ƃɂ��āA�����������i�V����w�j�́A�v�|���̒ʂ�q�ׂĂ��܂��B
�@�����{�@�ɂ�����u����̋@��ϓ��v�����́u������錠���̕����ۏ���w�@��ϓ��x�iequality of chance�j�Ƃ��Ē莮�������v���̂ł��邱�ƁA�u�o�ϓI�n�ʁv��t�������̂́A�������u�Љ�̌����ɂ����āA�o�ϓI�s�������@��ϓ��Ƃ����`���I�����̎�����j�ށv���ƁA�u�����I�ȕs�������A�`���I�����̊�b���@��������Ɓv��������邽�߁A�Ǝ咣���Ă���̂ł��i�w�����{�@���j�ƌ����A�V���{�o�Łx�j�B
�@�w�x�̂���ւ��͋ɂ߂Ė����ł��B
�@���҂݂̂��s�g�ł���u�I���̎��R�v�̎咣�����A�܂��ɐV���R��`�̐^�����ł��B�������Z�̓��p���͉�������ł��傤�B���R��������鎄�����Z���������邱�ƂƂȂ�ł��傤�B������̏k���E��̂́A���I�ɐi�s���܂��B
(4)�u���w�����̍č\�z�v�ƌ������̎��w�����팸
�@����Ɂw�x�́A�u�����Ԃ̕ی�ҕ��S�i���̐����v�Ƃ��āA�u���Ɨ��y�������Ə��w����g�ݍ��킹�Ă�葍���I�ȑ̌n�Ƃ���v���ƁA�u���ɁA�o�ϓI�ɍ���ȏɂ���{���ɑ��ẮA�c�ی�ҕ��S�i��������Ȃ����������悤���炩�̕�����������邱�Ƃ��K�v�v�Ƃ��Ă���
���B�����̕��ꎩ�̂́A���łɊݒm������Ɏ咣����Ă����Ƃ���ł���A�ڐV�����͂���܂��A��w�ɒ[�Ȍ`�Ŏ��s�����댯�����������Ƃ܂���K�v������܂��B�Ƃ�킯�A���w���Ƃ̃����N�́A���Ɨ��⏕�팸�E�S�p�ɓ����J�����̂Ƃ��āA�������邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�o�����ɂ��āA�w�x�́u����ꂽ��������w�����I�Ɏg�v�����Ƃ���{�p���Ƃ��A�u�č\�z�v�̓��e�����̂悤�Ɏ����܂��B�u���s�̏����̉ۑ�v�́A�u�������Z�̂Ƃ��ĐU������悤�ȏ����z���ɂȂ��Ă��邱�Ɓv�u������v�A���F�E���͂Â�����x�����邽�߂̏������K��
�����\���łȂ��v�_�ɂ��邱�ƁA�]���āA�u�����̏d�_���v�Ƃ��āA�u�������Z�̎���I�Ȏ��g�݂𑣂����i�I�ȋ������F���鋳��̎������d�_�I�Ɏx�����鏕���̎d�g�݁v�Ɂu�č\�z�v����Ƃ��Ă���̂ł��B
�@���Ȃ킿�A�o�����ɂ��Ă��g�[�ǂ��납�A�팸�̓���p�ӂ��A����������u�����̏d�_���v�Ə̂��A�������Z����ւ̎x�z�E�����}�낤�Ƃ�����̂ł��B�@�@
�@���̂悤�ȘH�����A���|�I�����̎��w�����R�����̓��ɒǂ����A�����������ꕔ�������Z�ɂ��ǐ肪�i�s���邱�Ƃ��w�x���g�͗\�����Ă���悤�ł��B�u�������Z���炪�ĕғ����ȂǂɎ��g�ޏꍇ�ɁA�����I�Ȗʂ��܂߂ĉ��炩�̎x�����s�Ȃ����Ƃ������v����Ƃ����w�x
�̎咣���A���̉����̏؍��ł��傤�B
�@
�R�D�������Z����E�o�c�ւ̎x�z�E���
(1)���ӓI�Ȍ����������S�_
�@�w�x�́A�u�{���A���P�[�g�v�������ɁA�����E�����̖������S�_��W�J���Ă��܂��B�������A�u�{���A���P�[�g�v�̕]���́A����߂ĈӐ}�I�E��דI�Ƃ���˂Ȃ�܂���B
�@�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�Ƃ������A������40���O��ɒB���鍂���ł��邱�Ƃ��w�x����ڂ��ɂ��Ă��Ȃ��̂́A����߂ĕs���R������ł��B�u���k�w���ɗ͓_��u��������v�u�w�ƕs�U�̐��k�ɑ��鋳��v�u���ׂĂ̐��k�ɑ��鋳��@��̕ۏ�v�u�i�w�̂��߂̋���v�u��b�w�͂̌���v���̐ݖ�ɑ��A�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�Ƃ̉�����ł����A���̂��Ƃ͉����Ӗ�����̂��B�{���́A�����������E�����Ƃ����ݒu�҂̕ʂȂ�������@�ւ̖ڎw���ׂ����R�̋���ڕW�Ɣ��f���Ă��邩��ɑ��Ȃ�܂���B����̏𗝂́A�����܂ł��Ȃ��A�����E�����̕ʂȂ��т�����ł��B��������ɁA�u�����E�����̖������S�v�Ƃ����ӂ邢�킯������ݖ�҂̓ƑP���A���̂悤�ȁu���ʁv�������炵�A���̐^�ӂ���ڂ����ނ��������A�ƌ���ׂ��ł��傤�B
(2)�����Ǝ��w���������}��Ƃ����������Z����ւ̉��
�@�������Z�̑��l���E���F���헪���A�ݒm���́u���Ԋ��́v�_�ɂ�鎄�w����̋A���ł��邱�Ƃɂ��ẮA���łɐG�ꂽ�ʂ�ł��B
�@�w�x�́A����ɘI���ɁA�������Z�����A���l���E���F��������Ă��܂��B�u�������Z���c�c�ߔN�̋�����v���i�̗���̂Ȃ��ŁA�}���ɓ��F����͂Â���̎��g�݂�i�߂Ă���B���������̉��A�������Z�́A�����w�A���̎��R�x�ƓƎ������������A�������Z�����鑽�l�Ȗ��͂Â����i�߂Ă����ׂ��ł���v�Ǝ咣���܂��B�w�x�̊��҂���u�������Z�����鑽�l�Ȗ��͂Â���v�Ƃ́A���{�u������v�v���O�����i�āj�v�������́u������v�v�ɂ��Ď����Ă�������A���Ȃ킿�A�u���ʉȁv�Ώd�����߁A�u�����w�ȁv��u���w�ȁv�Ȃǁu���l���v���邱�Ƃɂ���܂��B�u�i�w����v�̒ǔF��A�u���w�̐��_�ɂ��ƂÂ��@������������w�S�̋���x��l������v�̂����߂ȂǁA�X�[�p�[�G���[�g�Â���ƁA�u�]���ŏ���������v�J���҂̈琬���͂��鐭�{�E���E�̘J���͐���Ɏ������Z������]�������悤�Ƃ�����̂ł���_�ɒ��ӂ��K�v������܂��B
�@�����āA���łɌ����u���w�����̍č\�z�v��}��ɁA�������Z�Ɂu����I�A��̓I�ȉ��v�v�Ƃ��āA�u�{���̃j�[�Y�ɍ��킹�Ċw�Z�����v���Ă����s�f�̓w�͂��d�ˁA���Z�ɂȂ����F�E���͂�z���Ă������Ɓv���u�����v���߂Ă���̂ł��B�����炳�܂Ȏ������Z����ւ̉���ł͂���܂��B
(3)���w�o�c�ւ̉��
�@����݂̂Ȃ炸�A�w�x�́A���w�o�c�A�J�g�W�ɂ܂œy���œ��ݍ���ł��܂��B�u���߂��鎄�����Z���v�v�̑�Q���u���{�I�Ȍo�c���v�v�̒��ŁA���̂悤�Ɏ咣����̂ł��B
�@�u�c�c����܂ł̂悤�Ȍo�c�𑱂���Ȃ�A���Z�Ƃ��ĕK�v�Ƃ���
�鋳������̈ێ��͂��Ƃ��A�o�c���̂��̂����藧���Ȃ��Ȃ鋰�ꂷ�炠��v�Ƃ��A�u�]������̌ٗp�E���^�̌n�̌������v��u���ȕ]�����x�̓����v�A�u���E���̎�������⊈�����ɂȂ��錤�C�v������Č�����̂ł��i��11�j�B
�@�w�x�̂��̎咣�́A���o���̒菸�k����A�ꎞ���팸�A�����Г��ō̗p����Ă����ʂ̊����t���ٗp�Ɛ�C���@�s�̗p�E�s��[�Ȃnjٗp�̗������A���z�l����}���U���ɍ�����^����݂̂Ȃ炸�A����Ȃ�g������シ��댯�������߂���̂Ƃ��āA����y�����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�@�J���g���̓��z���ɁA���̂悤�ȁu���{�I�Ȍo�c���v�v��v������w�x�̗���́A�����w�Z�@�̖����鎄�w�i�o�c�j���w�Z�@�l�́u���含�v�Ɓu�������v�ւ̍s���̏d��ȐN�Ƃƌ���˂Ȃ�܂���B��������������A���{�̎�����́u�w�i���{�v�ɂ��u�������v�錾�Ƃ�������܂��B���{�ƒm���́A�����Ƃ̒c�̌��ɉ�����`�����ʂ����Ƃł������̂ł��傤���B
(4)�u�����J�Ɛ����ӔC�v�̎咣
�@�w�x�́A�������Z�Ɂu�����J�Ɛ����ӔC�v�����߂Ă��܂��B
�@�m���ɁA�u������V�v���܂ތo���ƍ����̌��J���u�������Z�ɑ�����I�����ւ̕{���̗�����ƂƂ��ɁA�L�������������@�ւƂ��Ď������Z���ʂ����ׂ��ӔC�v�ƒf�����_�́A�������̂���܂ł̉^���̔��f�ł���A�ϋɓI�Ӌ`��L������̂ł��B�������A�w�x�̋��߂�u�����J�v����{�I�ɍs���ƍ��E�̂��߂̂��̂ł��邱�Ƃ������Ƃ��킯�ɂ͂����܂���B�w�Z�Ƌ��E���́u���ȕ]���v�u�l���l�ہv���A���̑ΏۂƂȂ��Ă���ƌ���ׂ��ł��B���̈���ŁA����I�Ȋw�Z�]�c�����x�ȂǕ����k�́u�w�Z�Q���v�A�������E����c�̋c���^�̌��J�Ȃǁu�J���ꂽ���w�v���߂����u�����J�v�Ȃǂ́A�ނ�̎v�f�̚��O�ł��B
�S�D��㎄�����w�Z�����w�Z�A�����c�O��A���J����̉ʂ���������
�@��ɁA�w�x�́A�s���A�u�L���ҁv�A�����A�ꕔ�����ɂ�鍇��A�Ǝw�E���܂����B�������A�����̂����́A�ǂ̂悤�Ȗ������������̂��B
�@�u���k��v�̖ڎw���V���R��`�I���w�u����v�̖h�g��Ƃ��Ă̖����͂��납�A�ނ���A���̐��i�ɓ����J�����ʂƂȂ��Ă��邱�Ƃ��w�E������܂���B�R�c��ɂ�����ނ�̔��������̂��Ƃ������Ă��܂��i��12�j�B
(1)�@���J���̌����Ԃ̋������̐����Ə��w�����̊��p�@�@
�@���ʈψ��Ƃ��Ĉӌ��\���������J���́A�u�S�̂̒��ŋ����������v�Ƃ��A���̂��ƂŁu��������Ă������͓̂�������Ă����v�u�����̌��ʁA���鎄�w���Ȃ��Ȃ��Ă����̂́A��ނȂ��B�Љ�I�Ȏg�����Ȃ��Ȃ��Ă���̂�����v�ƌ�����܂����B
�@����Ɋ��J���́A�u������Ƃ������ƂɂȂ�A��菊���ŏ������Ă�����l�͂�����x���S���Ă��炤�v�A�u�w��i����1�F1.5���炢���K���v�Ƃ��A�u�������Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A�Ⴆ�Ώ��w���Ȃǂ��g���Ȃ���v�Ƃ���u�i�������v�_��W�J���܂����B
�@���łɌ��Ă����w�x�H���܂��A���J���̔����̎����_�͎��̂悤�ɐ����ł��܂��B
�@��P�́A�����Ԃ̋����������̂��������ƁA���̉��ŁA���w���u�Ԃ�Ă��d�����Ȃ��v�ƌ����������Ƃ́A�d��ł��B���Ȃ��Ƃ��u�������Z����U���̂�����v�Ɩ��ł������k��̐ȏ�A�ƊE�̍ō��ӔC�Ҏ��炪�A����܂ł́u���w�͈�A��Z���Ԃ��Ȃ��v�Ƃ����ƊE�̒c���̃X���[�K���𓊂��̂āA���������̊ѓO���咣�����̂ł��B���̊��J�����ɑ��A��c�O��́A�������Ɂu���X�Ԃŋ���������Ƃ������Ƃ͓��̒��ɑS�R�Ȃ������B�Ԃꂻ���Ȏ��w������A��������Ƃ������Ă���Ă����Ƃ������Ƃ��c�̂̔C���ƍl���Ă����v�ƈ٘_�������܂������A���J�����̏d�含�ɐG�����ꂽ���̂ƌ�����ł��傤�B�^�w���̒c�̌��ł́A�u���J����݂����ɉ��ł��K���ɘa�A����ꂽ�炽�܂�܂����B���J����Ƃ��͂�낵�����ȁB�������A���̂Ƃ��݂����Ȏ�҂́A����ł͂����܂���v�Ƃ����o�c�҂̊S�Q���A���J�����̔g��̍L������������̂ł��B
�@��Q�́A���J���́u�����i�������v�_�����̂܂܁w�x�ɐ�������Ă���_�ł��B���˂Ă��犘�J���́A�����Ԃ̕ی�ҕ��S�i���ɂ��āA�u�������Z����͐ŋ��̓�d�����v����������A���̂��Ƃ́u����̋@��ϓ��ɔ�����v�Ǝ咣���Ă��܂����i�u���w�W���[�i���v2000�N4�����j�B�������A�ς����������ꕉ�S�̌�����Œ肵�A���X�Ԃ̊w��i���ɂ��Ă͕s��ɕt���Ȃ���́u�����i��1�F1.5�v�_�́A�u�ŋ��̓�d�����v�����x�͌�������ɂ����߂邱�ƂƂȂ�܂��B
�@���̂��Ƃ́A���J���̋���ɑ��閳�m�A�u�@��ϓ��v�Ƃ͖����́u�w�Z���I�v���z���琶�ݏo���ꂽ���̂ƌ����ׂ��ł��B���������ł͂Ȃ����w���܂߂�����E�{����G�ɉ悤�Ȑl�����A��㎄�����A�̉�ɏA�C�������Ƃ́A�܂��ɑ�㎄�w�̕s�K�ƌ���˂Ȃ�܂���B
�@��R�ɁA���J���́A���{�����̔j�]��O��ɁA�u��菊���ŏ����ł��镃��v�̎��ȕ��S�Ə��w���̊��p���咣���A�w�x�́u���w�����̍č\�z�v��e�F�������Ƃł��B���łɌ��Ă����悤�ɁA�����̎咣�́A���J���̃I���W�i���ł͂���܂���B�ݒm������ȗ��̑��{�̎��w���������ŋ߂̎����}�u������v�v���̂��̂ł��B�u�����}�Ǝ�����ԁv���Ƃ����R�Ə����Ă������J���́A��㎄�����A�̉�Ƃ��āA���\�L�̊�@�ɂ��鎄�w�𐭌��}�̎�Ɉς˂悤�Ƃ����̂ł��傤���B
�@
(2)�u���{�I�Ȍo�c���v�v�Ɓu������V�̌��J�v���咣������c��
�@�w�x�̋N���̍ŏI�i�K�ŁA�u���{�I�Ȍo�c���v�v���}������܂������A����ɓ����J�����̂���c���̔����ł����B�w�x�́A�����n��ɏM�Ƃ��āA���Ɍ����悤�ɁA�u�ٗp�ƒ����̌������v���͂��߁A�u���ȕ]�����x�v��u���C���x�v�ɂ܂œ��ݍ��̂ł��B
�@�܂��A�u�v��i�w���v��Ⴍ�u���A�Ƃ�����c���̔����́A���w�G�S��掂��Ƃ�܂��A�w�x���S�O�Ǝ���̈������A�����̔������e�������ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�܂��A�u�\�͋��v�̓����͋���E�ɂ͍���Ƃ����c���̎咣�́A��ʂɂ����ĐϋɓI�Ӗ������܂����A�����ɁA�u�����̋��^�̌n�v���u��̖ڈ��v�Ƃ��Ă���_�ɁA���ӂ��K�v������܂��B�l���̐��̐i���x�ɂ���āA�u�\�͋��v���������蓾��A�Ƃ������Ƃ̕\���ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł�����B
�@������c�����A������V�̌��J�܂Ŏ咣�������Ƃ́A�w�x�́u�����J�Ɛ����ӔC�v�̎咣�ƌ��т������̂Ƃ͌����A���w�̌����������߂��ŐϋɓI�Ӌ`�������̂ł��B
�O�A�ǂ̂悤�Ɂw�x�H����j�~���A�u���S�ƐM���̊w���Â���v�������߂邩�B
�@�S�������A�͍�N�Ă̑S�����ŁA�u21���I���w��������v�\�A�u������͌���ł܂��Ȃ��A�������̌����̊m�����͂���v��{�����𖾂炩�ɂ��܂����B20���I��ʂ��Ċm�����ꂽ���̐��E�̌������킪���Ŋm�����邱�Ƃ����A���@�E�����{�@�̎w�������u����̋@��ϓ��v�A�����̋��猠�ۏ�̕����ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
�@�w�x�ɑ�\�����V���R��`�I����u���v�v�͗��j�̋t���ł��B���̑j�~�͍����I�ۑ�ł���A�l�ސi���̗��j�ւ̍v���ł��B���̂��Ƃ����炽�߂Ċm�F���A�w�x�Ƌ�̓I�ɐ茋�ԏ�ŁA�K�v�ȉۑ�ɂ��āA�G��Ă��������Ǝv���܂��B
�P�D�u����̋@��ϓ��v�Ɓu�ی�ҕ��S�i�������v�_
�@�w�x�́u�ی�ҕ��S�i�������v�_�Ɂu����̋@��ϓ��v������Λ�������ׂ��ł��邱�Ƃ́A�����܂ł�����܂���B
�@����������т��Čf���Ă����u������͌���Łv�Ƃ���������������A����������A���̉ۑ肩��A�v���[�`���܂��B
�@�w��S���̂��̂̌y�����͂���B���Ȃ��Ƃ��������Z�w��𐘂��u�����ƁB
�A�������Z�w��ɂ��ẮA�N���I�ɒl�������A��ʕ��������͂���B���̂��߁A�u�l�������v�ɂ��ĕ�U���鎄�w�����̎d�g�݂����߂�B
�Q�D�u�������e�䗦�v�́u�e�͉��v�_
�@�������e�䗦������������ꍇ�A���̊ϓ_���s���ł��B
�@��P�́A���łɐG�ꂽ�悤�ɁA�w��ꕉ�S�̔��{�I�Ȍy�����y��ɐ����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���̏�ŁA��Q�ɁA�����������̑S�������ʉȂւ̌v��i�w�������Ȃ��Ƃ��A��]�҂Ɍ������Ĉ����グ�邱�Ƃł��B���̂��Ƃ́A�S�������A�u21���I���w����v��u���{�̋�����v���Ƃ��ɍl�����v�̎����u��]�ґS���v�E�u���I�������v�ւ̓W�]�����̂ł��B
�@�����đ�R�ɁA�����E�������Z���A���q�����D�̋@��Ƃ��āA�w���K�́E�w�Z�K�͂̓K�������͂���A��������̍��ې��������͂���ϓ_����A�u���e�䗦�v�����肷�邱�Ƃ����߂��܂��B���������A���s�́u7�F3�V�F�A�[�v�ɂ��āA�������͊�{�I�ɍm�肷��]�������Ă��܂������A���̍����́A�����E�������Z�́u40�l�w���v���Z�̌��ʁA�u7�F3�v�ŕs�s�����Ȃ��������Ƃɂ��̍����������Ă��܂��B���̓_�ŁA�{�����A�s�������ƂƂ��Ɋw�Z�K�́E�w���K�͂̓K�����ɂ��ƂÂ��u�V�F�A�[�v�_�̍��肪���߂��܂��B
�@��S�ɁA�Ƃ�킯�������Z�ɁA���k�l�������ɑ��閯��I�K���͂������ɂ��肾���A�������邩���d�v�ȉۑ�ƂȂ�܂��B�厄���͂���܂ŁA��㎄�����A�́u���X�Ԋ����v����ɂ��āA�u�}�����̎��e���̎��сv����b���ɂ���Ȃǖ������͂�݂Ȃ�����A�u���k�����̔g��93�������Z�������ɋz�����A����̊w�Z���������k���̔�Q���W���I�Ɏ邱�Ƃ�����邽�߂̎���K���v�Ƃ��ĕ]�����A�e�w���̖���I���c�ɂ���Č����Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃ��Ăт����Ă��܂����B
���J�����A�������A��Ƃ��āA�ʂĂ��Ȃ����k�l���������ې����Ă��邱�Ƃ��猩�Ă��A��R�̊ϓ_�ƌ��т��A�e�������Z�́u���蓖�Đ��v�����炽�߂č���A����K�����m�F���������Ƃ́A����߂Đؔ������ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�厄���́A�u�������Z�������x�̉��P�ɂ��āv�Ƒ肷�铢�c�����s�A�u�אڂ��鎄�����Z���m�̍��������v���Ă������Ƃ��A����܂��i1997�N�j�B���̂悤�ȓ������x�̂�����ɂ��Ă���̉������߂��܂��B
�R�D���w����̎��含�ƌ�����
(1)���炽�߂Ď������Z�̑��l���E���F������̌���ɂ��āw�x���A���w����̎��含���A�V���R��`�I����u���v�v�𗦐���s����u����I�E��̓I���v�v�Ɋ�^��������Ɍ���E�U�����Ă��邱�ƁA���w�̌����������������j�A���w��������k���E��̘H���̐敺�ɗ��������Ƃ��Ă��邱�ƁA�ɂ��ẮA����܂Ō��Ă����ʂ�ł��B
�@�Ƃ�킯�A���]���u�Ւ��v�Ɗݒm���́u���Ԋ��͘_�v�ɂ�鎄�w����́u���F���E���l���v�̌��I�ȍL����A���̂��ƂŁu�i�w�v���E���ɁA����Y�Ƃƌ��܂�������̌�����@�ւ���̈�E�������鎄�����Z�̑��݂������ɁA���̈Ӑ}���т���悤�Ƃ��Ă���_�ɁA���̐[�����Ɛؔ���������܂��B���w�̎��含�A�����������炽�߂Ė₢������Ȃ���Ȃ�܂���B
(2)���w�̐i���I�`��
�@�������猤�����ҁu�������珬���T�v�́A�u���w�̗��j�����炩�ɂ��Ă���i���̓`���Ɠ����v�����̎O�_�ɂ킽���ĉ�����Ă��܂��B�u�@�w��Ƌ�����L���ΘJ�l���ɊJ�����Ă������ƁA�A���{�̊��ɑ��w��Ƌ���̓Ɨ�����낤�Ƃ��Ă������ƁA�B�Ɠ��̊w���A�Ǝ��̂����ꂽ������@�̗̍p�A�����ɂ��w��Ƌ���̐i���ւ̍v���c�v�B�@
�@���̎w�E�́A�u���w���A�������含�ƌ������i�����w�Z�@��P���j��y��ɂ����w���玩���́x�Ɂv�i�w���_���Ȃ��A���剻�������߁A�V�������w���x�A�ȉ��w���_���Ȃ��x1996�N9���A�厄���������Z�����s�ψ���j�̌Ăт����ƋO����ɂ�����̂ł���A�����ɕx��ł��܂��B
�@�Ƃ�킯�A�S���I�ɒ��ڂ���鎄�w�Ȃ�ł͂̋���Â���E�w�Z�Â���̎��H�ɋ��ʂ��Č�����������A�u�Ǝ��̂����ꂽ������@�̗̍p�v�ɂ��u�w��Ƌ���̐i���ւ̍v���v�Ƃ����_�ɂ��邱�Ƃ́A���̂��Ƃ̏؍��ł��i��13�j�B
(3)���Ǝ�`�E�卑��`�̊����玄�w����̓Ɨ�����邱�Ƃ����A���w�̎��含�̔����A�u�i��E�ݖ�̐��_�v�̔���
�@�܂��A�V���R��`�I����u���v�v���A�u���̊ہE�N����v�ُ̈�ȉ����t���A�u�_�̍��v�����A���璺��̗�^�Ƌ����{�@���������ȂǁA���Ǝ�`�E�卑��`�Ɩ������i�s���Ă��錻��A�����āu���̍��E���v�ƌ��т��ꕔ���w�o�c�҂̓����i��14�j������Ƃ��A�u���{�̊��ɑ��A�w��Ƌ���̓Ɨ�����낤�Ƃ��Ă����v���w�̐i���I�`���̌p���E���������A�܂��Ɏ��w�́u�i��E�ݖ�̐��_�v�̋�̓I�����Ƃ����ׂ��ł��i��15�j�B
�@(4)�@�������A���w�̎��含�ƌ������̓���ƐV���Ȕ����w���_���Ȃ��x�Ŏ������́A�u�w�������ƊǗ��E�^�c�̖��剻�E�������v�̏d�v�����w�E�A�u21���I���w��������v�ɂ����Ă��A�u�������含�ƌ������̓��ꂱ�����{�I���w�����̍����I�R���Z���T�X�̑O��v�Ƌ������Ă��܂��B
�@�w�������̑S�ʌ��J�ƕ���E���k�Q���̖���I�w���Â���������߂邱�Ƃ����߂��܂��B
�@�����ɁA�w�x�́A�u�@������v�𐄏����Ă��܂����A���̂��Ƃ́A�����}�̏@������𗘗p�����u�S�̋���v�̐��i�Ɛ[�����т��Ă��܂��B���������������Z�ɂ�����@������̂��肩���ɂ��āA�厄���͂��ł�1980�N9���u�w����c���w�x�̌������Ăт�����v�ɂ����āA�w�E���Ă����Ƃ���ł����i��.16�j�A�����A����I�w�c�̑���������@20���Ƃ̊֘A�ɂ����āA�����^�O����N����Ă���A�����E�����������߂��܂��i��17�j�B���Ȃ��Ƃ��A�ݗ��@�l�̓���@�����炪�K�C�Ȗڂɑg�ݓ�����Ă�����A���k�E���E�������@���s���ɏo�Ȃ���������悤�Ȏ��ԁA����ɗ������E�����\���Ȃǂɂ����āA�w�Z�@�l���@���@�l�ɏ]�����Ă���悤�Ȏ��Ԃ��A���̂܂ܕ��u�����Ȃ�A���̂悤�Ȋw�Z�@�l�ւ̌��I�⏕���A���@89���ᔽ�̋^����������邱�Ƃ́A���R������ł��B
������
�P�D�u�����ƑI���v���A�u�Q���Ƌ����v���@
�@�w�x�͊w�Z�E������u���i�v�Ƃ��A�������ʂɂ킽��u�I���̎��R�v���������܂��B�����ɂ͊w�Z�Â���E����Â���ɂ�����A����E���E���E���k�̋����͂܂��������荞�ޗ]�n������܂���B
�@���E�l���錾�i1949�N�j��26���u����Ɋւ��錠���v�́A��P���Łu���ׂĐl�͋�����錠����L����v��搂��A��Q���ł͋���̖ړI�ɂ��āu����͐l�i�̊��S�Ȕ��W���тɐl���y�ъ�{�I���R�̑��d�̋�����ړI�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�����ŁA��R���ŁA���̂��߂ɂ́u�e�͎q�ɗ^���鋳��̎�ނ�I�����錠����L����v�Ƃ��Ă��܂��B�u�I���̎��R�v�͖{������E�����̋��猠��ۏႷ�邽�߂̂��̂ł����āA�����ċ���Ɂu�s�ꌴ���E���������v���ѓO�����w�Z���u����Y�Ɓv�����邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��A�܂��Ă�q�ǂ��E�N�����ʂ��I�ʂ��邽�߂̂��̂ɂ��Ă͂Ȃ�܂���B
�@�u�����ƑI���v���A�u�Q���Ƌ����v���́A�s���މ�̑Ό��_�ƂȂ��Ă��܂��B�������́A��N�Ĉȗ��A�u����E���k�Q���̐V�����w�Z�Â���v��A�u��㎄�w�����������߂��v����20���N���}���鍡�H�̎��w�f�[�W����A���̑�P���ƈʒu�t���܂����B���̐����A�Ƃ�킯���k�̎Q���Ɓu�ӌ��\���v�����߂��܂��B
�Q�D���w�U�������@�������ً̋}��
�@����܂Ť�������͌��s���w�U�������@�̌��E�Ɩ��_�ɂ��Ă����Ίm�F���Ă��܂����B����́w�x���A������ς���A�U�������@�̘g���ł̎咣�Ƃ������ʂ�����܂��B���@��R���i�w�Z�@�l�̐Ӗ��j�́A�u�w�Z�@�l�́A���̖@���̖ړI�ɂ��݁A����I�ɂ��̍�����Ղ̋�����}��A���̐ݒu����w�Z�ɍ݊w���鎙���A���k�A�w�����͗c���ɌW��C�w��̌o�ϓI���S�̓K������}��ƂƂ��ɁA���Y�w�Z�̋��琅���̌���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�Ă���̂ł��B�u����I�ɂ��̍�����Ղ̋�����}�v�邱�Ƃ͊w�Z�@�l�̐Ӗ��A�Ȃ̂ł��B
�@���̑�R���́A����s���{���{�����w�����̖@�I�Ӗ�������������Ƃ̑�ւƂ��ċK�肳��܂����B
�@�w�x�̎��w�����팸�A�������Z�́u����I�E��̓I���v�v�̗v���Ƃ�����{�I�\�}�ƁA�{���I�Ɉ�v������̂ł��B
�@�S�������A�u21���I���w��������v�́A�V���Ȏ��w�����@�̈��Ƃ��āu���w�����ɕ��S�@�v�i���́j���f���Ă��܂��B��ǂ������߂܂��B
�@�R�D�u�~�肩����̕������������v�Ɓu�Ό���f���������v����������
�@�w�x�̂����W�J���Ȏ��w�u�U���v��́A���|�I�����̎������Z���u���R�����v�̕��ɒǂ����A�ق�̈ꈬ��̎������Z�̑����ƉǓ��x�z����\�肵�Ă��܂��B���̘H���́A���w�o�c�҂̊Ԃɂ����Ă��A���������������Ƃ��Č��݉����A�u�����}�ɛZ�тւ炤�v����܂ł̍앗�����I�ɓ]������͂Ə��������肾���ł��傤�B
�@�������́A�ߓ��̑�52��Վ�����Łw�x�H�����ӂ̓������j���m�����܂����B
�@�w�Z���p�����̂��������i�̕������������j�ƁA�u�����H����x�C�G���A�J���Ȃǖ��ʂȑ�^�v���W�F�N�g����߂āA����E�����D��̕{���ɐ�ւ���v�u�{���ƍ����̊v�V�v�i�Ό���f�����j�����ѕt���A�O�ꂵ���Q���Ƌ����ɂ��L��Ȑw�n���\�z���A�����̂��߂̎��w�A�u���S�ƐM���̊w���Â���v�Ɍ����đO�i���܂��傤�B
|
|
|
|
Copyright 2009 ��㎄�w���E���g���i�厄���j