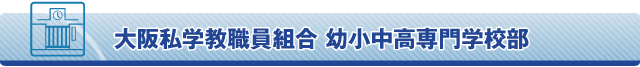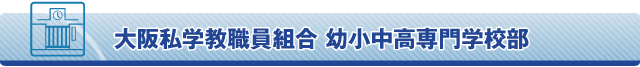討議資料・見解・私学おおさか
|
2009/2/16
| | 「教師不適格」論の克服のために | | "
目次
一、あい次ぐ「教師不適格」判決・命令
二、教育のいとなみへの無理解〜問われる裁判所の教育観・学校観
1.「教育は管理」の学校観・教師観
ア、教師と生徒の人間的触れ合いに教育的価値を認めない
イ、生徒をもの扱いする管理教育
ウ、「教師は生徒を信じてはいけない」
2.教師の専門性と自主的権限の否定
3.無責任な「教師不適格」論〜「矯正不能」の判断の基準は?
ア、「不適格」とはどういう意味か
イ、教員免許は「適格性」の証し?
4.労働者の生活権、労働権の軽視は、教育反動化と一体
三、民主的教師・教育論と学校論で「教師不適格論」の克服を
1.大衆的裁判闘争の前進のために
2.民主的教師論に学ぶ
3.懲戒からの保護と同僚の援助
4.多彩な教師たちのアンサンブルの教育的価値
5.視野広く
はじめに
中教審路線と生徒減のなかで、生き残りを賭けた私学経営者の経営戦略は、「管理と競争」、 「差別と選別」の教育の強化を軸に推進されていますが、それは同時に、
◎リストラ「合理化」と劣悪な教育労働条件の押しつけ
◎期限付き雇用の拡大と教職員への能力主義的・成績主義的管理の強化
◎それらを通じた個別的労使関係の拡大と集団的労使関係の形骸化、組合の弱体化など、教職員の分断と状態の悪化、権利への攻撃の強化をともなわざるを得ません。
そのなかで、最近、教師としての「適格性」に藉口した解雇攻撃や教職員差別〜しばしば不当労働行為意思が隠蔽されている〜があい次ぎ、裁判所も判決や命令のなかでこれを容認する例が増えています。このことは、いじめ、登校拒否、体罰、教師の非行の続出など、学校と教師への不信が社会的にひろがっているいるなかだけに、なおのこと見逃すことができず、これに的確に反撃することが求められています。
「教員不適格論」による解雇攻撃に対しては、すでに東京・松蔭学園のたたかいが水準の高い判決(93年6月23日、東京地裁)をかちとっていますが、「教員不適格」論に対しては、職場でも法廷でも、民主的教師・教育論と学校論を正面に据えた反撃が重要であることがますます明らかになっています。
以下、大阪の経験について報告します。
一一、あい次ぐ「教師不適格」判決・命令命令
東洋家政の林教諭は、3年生3人に、1年生世界史Aの答案十数枚を「採点させた行為」 (もちろん、後で林教諭自ら点検し、正確を期している)が「教員としての適格性に欠点がある」「重大な義務違反」という理由で解雇され、大阪地裁への身分保全仮処分請求も却下されました。開智高校・近藤教諭の仮処分裁判(和歌山地裁)敗訴の理由は、定期考査の出題が 「不適切」であった、「感情の赴くまま」一方的に授業放棄、生徒を混乱させて自己の退職騒動に巻き込み職場を放棄した、などで、和歌山地裁によると、これらは「教職員としてその言動に適格性を欠く」というわけです。また一生徒への人権侵害事件を理由に懲戒解雇された大商学園・大島教諭は、仮処分裁判では勝ったものの、本訴では大阪地裁の中路裁判官は、学園による「予備的解雇」を認め、大島教諭の逆転敗訴となりました。大島教諭が、仮処分勝利後、学園の禁止通知を無視して水泳部の指導を行ったのは「独断専行」で「職場規律」を乱したなど、「教員不適格」が理由です。
一方、住吉学園・大浦教諭の場合は、大阪地裁での仮処分に続いて本訴でも勝ったものの、裁判所(中路裁判官)自らが、大浦教諭の生徒指導の熱意、方法が不十分、入試説明会でのビラ配布、「管理職と原告の間で考え方にズレがある」などを理由に、「原告が住吉学園の教師として適当かどうかについて、疑問の余地がないわけではない」とし、学園を勇気づける始末です。
二二、教育のいとなみへの無理解〜問われる裁判所の教育観・学校観校観
これら一連の判決・命令に見られる裁判所の教育観は、以下に述べるように、憲法や教育基本法の示す教育の姿からは程遠く、かって東京地裁が、教育について、「人間が人間に働きかけ、児童・生徒の可能性を引き出すための高度の精神的活動」とした(第2次教科書裁判S45・7・17東京地裁・杉本判決)ような見地は、薬にしたくも見あたりません。そこに見られる生徒観は、無限の発達の可能性をひめた学習の主体というよりは、受験戦争の中で1点を争う点数競争に汲々とし、いつ不正や悪事をはたらくかわからない存在、学校と教師に管理される対象と見做すもので、教師もまた、「国民に対する直接の責任」(教育基本法第10条)を負った「全体の奉仕者」(同第6条)どころか、理事会・校長の管理・統制に従属する単なる従業員にされています。
1.『教育は管理』の学校観・教師観
ア、教師と生徒の人間的ふれあいに教育的価値を認めない
これらの判決や決定に共通して見られる第一の問題点は、教育基本法の言う教育の目的(人格の形成)や教育の本質(教師と生徒の豊かな人間的ふれあいを通じて訓育・陶冶が行われる)を無視していることです。例えば、和歌山地裁は、「大学受験をひかえた重要な時期ある三年の生徒」「大学受験を控え試験の結果に一喜一憂しがちな生徒」に対し、近藤教諭が「いま退職願を出してきた。私は今日で学校を辞める。君達は受験をひかえた大事な時期だから、私の教えを守ってこれからも頑張ってほしい」旨の別れの挨拶?をして退出したことをもって、「生徒が廊下に出る等の混乱状態を外形的にも生じさせた」「生徒を自己の退職騒動に巻き込んだ」と非難しています。
しかし、その「混乱状態」はすぐに収まり混乱というほどではなかったことは、稲田校長自身が証言するところですが、なによりも生徒たちが、近藤教諭に対して退職を思いとどまるよう泣いて懇願し、そのうえ学校に対しても近藤教諭を退職させないよう嘆願書を提出している事実を、裁判所は無視したのです。
イ、生徒をモノ扱いする管理教育
また、大阪地裁の中路裁判官は住吉学園事件判決で、学園が裁判用に作成・提出した資料をもとに、大浦教諭の担任クラスの「遅刻・早退回数が長年にわたって常に多く、全クラス中最悪かそれに近い状態にある」「その原因…の相当部分は、原告の指導力や熱意等との関わりが存することは否定しがたい」「原告の生徒指導がその熱意、方法において、充分なものであったかは極めて疑わしい」「本訴において綺麗ごとに終始した主張ないし供述をしているが、到底措信することはできない」などと一方的に決めつけています。これは、生徒を生きた人間としてではなく、モノとして扱う管理主義の立場です。
兵庫高塚高校の生徒の校門圧死事件は、遅刻をなくする取り組みが数と%で追求されるとどういう結果をもたらすかを全国の父母と教師に教えました。
三上満氏も『学校ここにある希望』で紹介しているように、「こどもたちをモノとして見たときに追求されるのは数と%」です。大浦教諭に不足していたのは、本当の生徒指導とは無緑の管理主義の 「熱意」だったのです。ところが裁判所は、大浦教諭の教育的所信の主張を、吟味するどころか「綺麗ごと」として一蹴する始末です。
ウ、「教師は生徒を信じてはいけない」?
その点、東洋家政事件の岩崎決定もひどいものです。これは、「正誤づけしている生徒が誠実な生徒であったかどうかはともかく」「監視のゆきとどかないところでは、どのような不測の事態、たとえば、他の生徒が来て本件答案用紙を見たり、正誤づけをしたり、場合によっては解答を変えたりする可能性もあった」など、そもそも事実認定さえ放棄した「証拠裁判主義にも明らかに反する」(田原俊雄弁護士・『私学判決命令集vol.4』)ものですが、ここに見られるのは、頭から生徒を疑ってかかる態度、まるで「人を見たらどろぼうと思え」といわんばかりの態度で、裁判官の生徒観のひどさを示しています。
2.教師の専門性と自主的権限の否定
一連の判決・決定に見られる第二の問題点は、憲法23条(学問の自由)や26条(教育を受ける権利)および教育基本法第6条(学校教育)、第10条(教育行政)第1項が、教師の教育の自由(教授の自由)ないし教育上の自主的権限を保障しているにもかかわらず、これらを認めないか、厳しく制限する立場に立っていることです。
大浦教諭は、「管理職と原告の間で考え方にズレがある」ことを、どうズレているかの吟味もなく「学園の教師として適格かどうかの疑い」のある理由とされ、大商学園大島教諭も、仮処分勝利・本訴係争中に水泳部の指導を生徒、父母、水連関係者から乞われて行い、学園の無謀な禁止命令を無視したことを「独断専行」「職場規律を破った」とされました。
裁判官が描くのは上命下服の職場秩序です。たとえ上司の命令が教育の条理に反する不当なものであっても、これに従うべきだというわけです。ここには「教育は不当な支配に服することなく国民全体に対して直接責任を負う」(教育基本法第10条)や、「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚しその職責の遂行に努めなければならない」(同第6条第2項)といった見地は見られません。したがって教師の専門性に対する尊重など、まったく見られないのも当然と言うべきでしょう。
教師の専門性については、すでにILO・UNESCO「教師の地位に関する勧告」も、 「教員は職務の遂行に当たって、学問の自由(Academic Freedom)を享受するもの」としており、その専門性は「自由の雰囲気」のなかではじめて発揮されるということは、第1次教科書訴訟・高津判決(S49・7・16)も認めるところです。もちろん、生徒個人の成績評価も、「まさに具体的教育活動に属し、担当教師のみがなしうる事項であり、教育行政機関に許されるところではない」(仙台高裁・岩手県教組事件判決S44・2・19)とされ、東京・松蔭学園東京地裁判決も、教師による成績評価の専門的教育的裁量権を認めています。ところが、「生徒採点問題」(東洋家政事件)や「出題内容の不公平」(開智高校事件)など裁判所の判断には、教師の教育(教授)の自由や成績評価権を尊重する見地はまったくありません。なお、学校教育法第28条4項の「教諭は児童の教育を掌る」の規定は、単に管理者の指示や方針にしたがって授業をしたり、生徒「管理」を行ったりするにとどまらず、教師個人もしくは集団としての「教育課程編成・実施権、教科書採択権、教材決定権、成績評価権、児童生徒懲戒権、学級運営権、研修権等」の自由ないし権限を認めたものとされています。(『教育労働者の権利(上)』S46・7 p 351)
3.無責任な「教師不適格」論−「矯正不能」の判断の根拠は?
ア、「不適格」とはどういうことか
公務員の場合、「降任・免職の事由」は、 勤務実績が良くない場合 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えない場合 前2号に規定する場合のほか、 その職に必要な適格性を欠く場合、ときれています(地公法第28条1頃、国公法第78条)。私学の教師は公務員ではありませんが、「国民に直接責任を負う」「全体の奉仕者」という点では公務員と共通です。しかし、「勤務実績不良、心身の故障、適格性の欠如などといってもその程度は千差万別です。その点、判例は、「当人の素質、能力、性格等からいって公務員たるに適しない色彩またはしみが付着していて、それが簡単には矯正できない持続性を持っている場合を言う」(大阪地裁S27・5・6 『教育労働者の権利(上)』p.247)とか、「簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合を言う」(最高裁第2小法廷S48・9・14、長束小学校事件)と、「適格性」判断に厳格性を求めており、たとえミスがあっても矯正が期待できる場合は、免職・降任の処分は行えないとしています。その点、東京・松蔭学園森教諭(組合委員長)を被告として学園側が解雇の正当性を主張して争った事件で、東京地裁遠藤判決(H5・6・23)が、「被告の本件ミスは、これが生徒に及ぼす影響等からすれば、軽微な誤りであるとは言えないことは明かであるが、それが被告の能力、素質、性格にもとづくものであって矯正が容易でないものとは到底認められず、したがって、本件ミスによって、被告に教師としての職務の適格性が欠けていたとまではいえないとしたのは注目されるところです。
イ、教員免許は「適格性」の証し?
おまけに教員の教育上の能力や資質は、現行法制上は「教育職員免許制度によって認定されており、免許状付与によって教育上の能力や資質が言わば公認されたと見るべきで、免許状を保有している者に対して教員としての教育上の能力、資質(適格性)を欠いていると認定することは、免許制度の趣旨を没却するもの」との説もあります(『教育労働者の権利(上)』p.248)。これによると、教員の場合には、児童・生徒に体罰を加える(学校教育法第11条但書違反)傾向が改まらないとか、無断欠勤が多いとか、いわば教育外的・外形的事項のみが、その勤務実績や適格性の判断において問題とされうることになります。いずれにしても、大阪地裁や和歌山地裁が、なんの論証もなくきわめて安易に「教員不適格」のレッテルを貼って顧るところがないのは許せません。
4.労働者の生活権、労働権の軽視は、教育反動化と一体
解雇は労働者の生活権や労働権をも奪ういわば死刑にひとしい極刑で、よほどのことがない限り認めるべきではありませんが、大浦事件を除く3つの判決にはこのような見地はなく、使用者の「解雇の自由」をいとも簡単に幅広く認める結果になっています。その点、先にあげた長束小学校事件の最高裁第2小法廷判決も、「その職に必要な適格性を欠く場合」の分限処分について、任命権者の裁量的判断の余地は、「免職」の場合は「降任」の場合よりも狭いとしています。
今日、労働者の生活や権利は、職場における団結権や団体交渉権の確立を通じて辛うじて守られ、教師の専門性もまた教職員の団結によってはじめて実現されるという状況では、使用者の「解雇の自由」が厳しく制限されなければならないのはいうまでもありません。特に「競争原理・市場原理」に曝された私学経営者が学園の私物化や管理・統制を強化する一方、リストラ「合理化」と組合弱体化の目的で行う「教師不適格」攻撃に裁判所が手を貸すことは、私学教職員の生活権、労働権を守る上からも、また中教審路線に対決して憲法・教育基本法の支配する学校づくりをすすめる上でも、断じて許せません。
三、民主的教師・教育論と学校論で「教員不適格論」克服を
「教師不適格論」による攻撃は、教師とは何か、学校とは、教育とはなにか、を改めて考えさせる契機となっています。なぜなら、「教師不適格論」は教師の「適格性」とはなにか、を問い返す結果となり、教師の「適格性」は、憲法や教育基本法が命じる教育の目的や課題、そこでの教師の責務などから離れて論じることができないからです。
いま橋本内閣と財界、中教審は、「教育改革」の名で、教育と学校の反動的再編、教師への統制と支配を強めようとしています。これに対して国民の側からも、民主的な教育改革・学校改革を求める世論と運動が高まっていますが、私学教職員が自らの生活と権利、雇用を守る上で、また日本の教師の一員としての使命を果たし教育の利益を守っていく上で、「教育・学校・教師そもそも論」に強くなることは、避けて通れない課題となっています。
1.大衆的裁判闘争の前進のために
職場と学校、争議団と弁護団で旺盛な「教育・教師そもそも論」をたたかわすことです。
「弁護士や検察官の理論的水準の高さということもまた、裁判官が水準の高いすぐれた判決を出す一つの重要な要因」(渡辺洋三『法を学ぶ』岩波新書p.203)です。だとすれば、裁判官や判決のひどさを詰るだけではなく、こちらの「水準」を高める努力が必要です。職場と学校を基礎に、憲法と教育基本法が日本の教育と学校、教師になにを求めているかを明かにしつつ、裁判闘争を弁護士任せにせず、被解雇者や組合も加わった学習と討論で大衆的裁判闘争を前進させることがますます重要になっています。
2.民主的教師論に学ぶ
被解雇者にも、敵に攻撃を許す弱さがある場合があります。必要で適切な批判と自己批判によって弱点を克服することは、たたかいの前進にとってはもちろん、被解雇者自身の成長にとっても大切です。
その際、
ア.教育と教師の責務、「国民に対する直接の責任の自覚
イ.教師集団の一員としての規律と組織性、ある程度 職場にとげ 込む能力
ウ.生徒をどう見るか、権利の主体として見ているか
などがポイントになるでしょう。
「教師論」をすすめるうえで大切なことは、教師に求められる専門職としての厳しさの強調だけではなく、教師は常に「未完成」であること、それは、教師のはたらきかける対象が一人一人異なった個性とかけがえのない人格を持つ人間であり、しかも子どもの発達は予測しがたい速度と態様をしめすこと、そして知識や技術は不断に進歩するにもかかわらず個々の教師の知見や技術には限りがある、など、そもそも教育の仕事の本質に根差しているもので、したがってはじめから完成された教師などはどこにもなく、教師は「教師に育つ」のだという見地(統一労組懇教職員部会『新教職員読本』学習の友社 1985)を貫くことです。
3.懲戒からの保護と同僚の援助
ILO・UNESCO「教師の地位に関する勧告」は、「教員団体は懲戒問題を扱う機関の設置に当たって、協議にあずからなければならない」(49項)とし、弁護の権利、不服申立の権利など、懲戒手続きの各段階で「公平な保護」を受けるべきとしています(50項)が、続いて「懲戒からの保護、ならびに懲戒それ自体の効果は、その教員が、同僚の参加のもとで判定を受ける場合非常に高まる、ということを当局は認識しなければならない」(51項)としているのは重要です。
体罰など教育(生徒指導)の内容や方法が間違っている場合、具体的な状況によっては一定の懲戒が避けられない場合もありますが、その場合でも、教師集団全体の問題として処理すべきであって、校長や管理職が一方的に判断するのは問題です。ましてや理事会が現場の頭越しに懲戒権を振り回すなどは、もってのほかです。
4.多彩な教師たちのアンサンブルの教育的価値
いま能力主義、実績主義の浸透と管理体制の強まりの中で、個々の教師の「能力」や「適性」を問題にする傾向が強まっています。当然のことながら、個々の教師には、生育歴の違いなどから教育的力量や民主的訓練の度合いには違いがあるうえ、学年や教科、職員会議など職場環境にも、それぞれ民主的到達度にさまざまな制約があります。そのなかで、「未完成」で「不完全」な教師がなぜ社会進歩に貢献できるか、など「教師論」を深めつつ、教師集団の人間的アンサンブルの教育的価値、学校に人間を取り戻すための多彩な教師のアンサンブルの大切さを、職場と学校全体の合意にすることが求められています。その点、次の指摘は、大きな示唆に富んでいます。
「人間の弱さとか悲しさを身体全体に漂わせているような先生も、ほくはいなきゃいけないと思うし、そういう先生だってやっぱり何かを子どもに伝えているはずなんですよね」
「子どもたちというのは、本当に人間らしい先生というのを求めている。また先生の失敗が大好きでね。人間らしい失敗をしたり、或いは人間的な不完全さを見せてくれる先生、さっきいろいろなタイプの先生がいるとおっしゃいましたが、無口な先生もいればちょっとずっこけた先生もいる。いろいろな先生がいる。そういう人間的な不完全さみたいなものを通して味わえる『人間っていいな』という実感、そういうものをすごく求めているのですね」(山田洋次・三上満『めんどうくさいもの人間・映画、教育そして愛』労働旬報社)
5.視野広く
「規制緩和」の名による労働法制改悪は、労働者のいのちと健康、生活と権利をいっそう破壊しようとしています。日経連と財界は、こともあろうに「人間尊重・個性重視」のかけ声で、差別と競争、管理と統制の労務政策を強め、リストラ「合理化」をすすめています。
これに呼応するように、第15期・第16期中教審も、「個性重視」「たくましく生きる力を」など欺瞞的な手口で、差別と選別、「管理と競争」の体制を強め、学校と教育から人間らしさをさらに奪いさろうとしています。そして橋本「教育改革」は、財政破綻を口実に、「第6次(高校第5次)教員定数改善計画」の凍結や私学助成の「思い切った抑制」を実行に移そうとしています。
私学のたたかい、特に解雇撤回闘争では、ときに「経営者主敵論」に陥りがちです。しかし私学もまた社会現象、政治現象です。「敵以外は味方」−−「味方以外は敵」ではなく−−の立場に立って、職場と地域、学校と教育、それに裁判所の教育観を変える展望とそれにふさわしい構えが求められる所以です。
"
|
|
|
|
Copyright 2009 大阪私学教職員組合(大私教)